- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30
- 最終受付時間19:00
- 定休日木・日・祝
兵庫県姫路市別所町北宿1046−3

筋肉の緊張・疲労・姿勢の乱れ(デスクワーク・スマホ姿勢など)
神経関連:肩甲背神経(C5など)の圧迫・痺れ
関節・骨格:椎間関節症、棘上靭帯炎、ぎっくり背中など急性症状
内臓由来の関連痛:心疾患(狭心症・心筋梗塞・大動脈解離)、胆石症・胆のう炎・膵炎など、肺・胸膜の関連痛
患部を動かした時に痛む?(筋/関節の可能性)
姿勢を変えても痛む?(姿勢・神経起因)
痺れや力の入りにくさがある?(神経圧迫)
安静時・呼吸時に痛む?(内臓・胸膜関連の可能性)
ストレッチ・姿勢改善・運動習慣、エルゴノミクス(椅子・枕)
RICE療法・温熱療法・抗炎症薬の使い方(市販・湿布など)
症状が長引く・強い・しびれ・発熱等ある場合は整形外科・神経内科・内科へ
急性激痛・冷や汗・呼吸困難などは心疾患の可能性として即受診を
実際の改善例(アールカイロの症例など)

「肩甲骨の真ん中が痛い」と訴える方の多くは、筋肉の疲労や姿勢の崩れが影響していると言われています。特にデスクワークやスマホ操作の時間が長い人は、背中の筋肉が常に緊張しやすくなる傾向があります。BLBはり灸整骨院やさかぐち整骨院の情報でも、同じ姿勢を長時間続けることが痛みにつながると説明されています。
肩甲骨の痛みは、神経が関与している場合もあります。桃谷整形外科によると、肩甲背神経(C5など)の圧迫や障害があると、痛みやしびれを感じやすいとされています。単なる筋肉の疲労とは異なり、しびれや感覚異常を伴うケースも少なくないようです。
リハサクなどの整形分野の解説では、椎間関節症や棘上靭帯炎が肩甲骨周辺の痛みを起こす一因とされています。また「ぎっくり背中」と呼ばれる急性の痛みも、関節や靭帯の負担から生じると言われています。これらは突発的に強い痛みが出るため、筋肉性の痛みと区別することが大切です。
一見背中とは関係なさそうですが、内臓の不調が肩甲骨の痛みとして現れることがあります。メディカルノートやくすりの窓口、アリナミンの情報では、心疾患(狭心症・心筋梗塞・大動脈解離)、胆石症や胆のう炎、膵炎、さらには肺や胸膜の炎症などが原因になるケースもあると紹介されています。症状検索エンジン「ユビー」や富士薬品の情報でも、内臓疾患が背中の違和感として表れることがあると言われています。
肩甲骨の真ん中の痛みは、単純な筋肉疲労から神経障害、さらに内臓の関連痛まで幅広い要因が考えられます。放置してしまうと悪化する可能性もあるため、セルフケアで改善しない場合は専門機関に相談することが重要です。
#肩甲骨の痛み #筋肉疲労 #神経圧迫 #姿勢改善 #内臓関連痛

「腕を上げたり後ろに回したりした時に肩甲骨の真ん中が痛むんです」という声はよく聞かれます。これは筋肉や関節の動きに負担がかかっているケースが多いと言われています。特に肩甲骨周辺の筋肉は、デスクワークや長時間の同じ姿勢で硬くなりやすい傾向があります(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/7085/)。
「姿勢を変えても痛みが続くんですが…」という場合は、筋肉だけでなく神経が関与している可能性もあるとされています。猫背やスマホ姿勢などによって神経が圧迫されると、違和感が残ると言われています(引用元:https://momodani-usui-seikei.com/column/)。
「痛いだけじゃなくて、手までしびれる気がする」という相談も少なくありません。これは神経が圧迫されているサインである可能性があるとされ、筋肉の疲労とは区別が必要だと解説されています(引用元:https://medicalnote.jp/symptoms/肩甲骨が痛い)。力が入りにくい感覚も併せて注意が必要だと言われています。
「動いてなくてもズキズキする」「呼吸をすると背中に響く」という場合は、内臓や胸膜に関連した痛みの可能性も考えられるとされています。心疾患や肺の不調などが背中の違和感として現れることもあると言われています(引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/scapula-pain)。これは放置せず、早めに専門機関に相談することがすすめられています。
#肩甲骨の痛み #セルフチェック #神経圧迫 #姿勢の乱れ #内臓関連痛
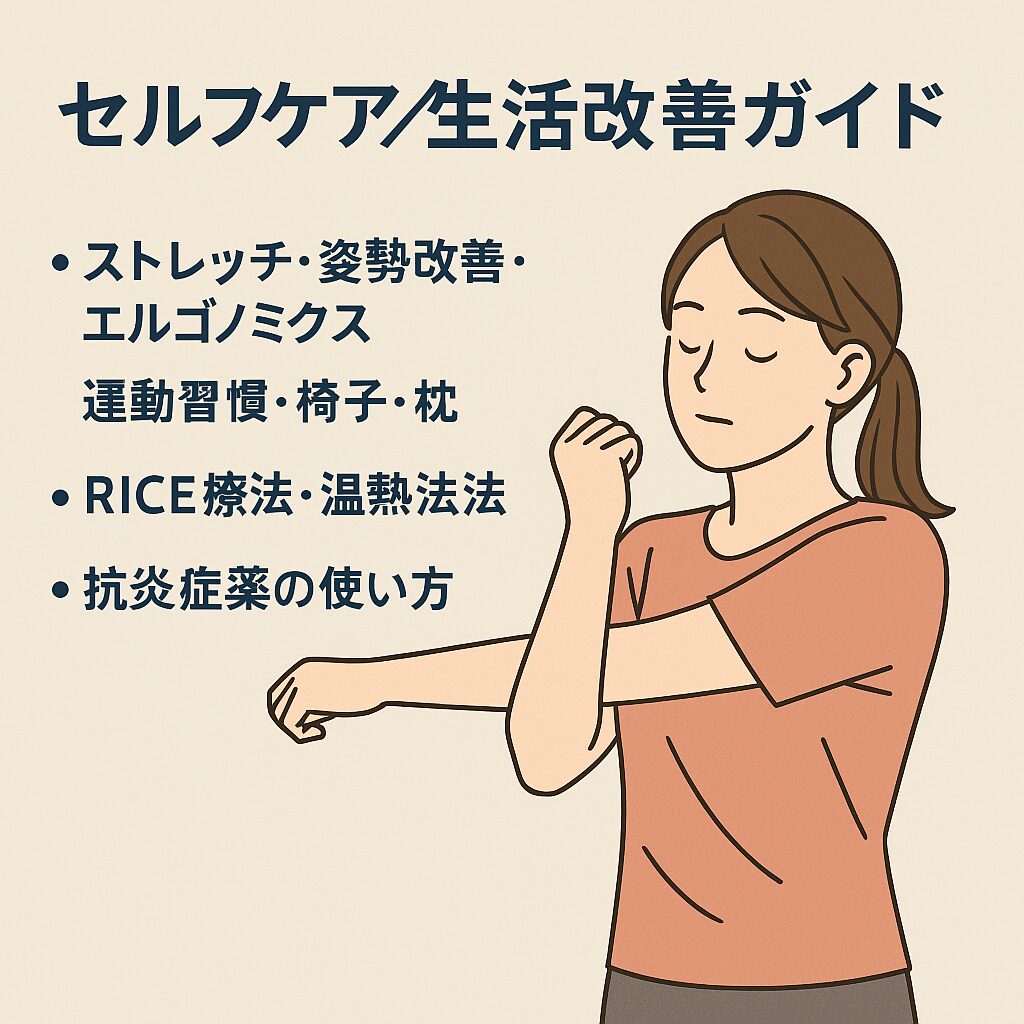
肩甲骨の真ん中の痛みを和らげるためには、まず日常生活の工夫が大切だと言われています。BLBはり灸整骨院やリハサクなどでも紹介されているように、軽いストレッチを取り入れることで筋肉の緊張を和らげやすくなるそうです。特に「肩を回す」「胸を開く」といった簡単な動きは、デスクワークの合間に行いやすいとされています。
さらに、椅子や枕といったエルゴノミクスの工夫も効果的と言われています。富士薬品公式通販の情報では、自分の体格に合ったサポートグッズを選ぶことが、痛みの予防や改善につながると紹介されています。
急に痛みが強くなった場合には「RICE療法」が参考になると言われています。これは、Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字を取ったもので、スポーツ障害などでも広く使われる方法です。リハサクの情報によると、初期の痛みが強い時には冷却を、慢性的なこりや張りには温熱療法が有効だと解説されています。
一方で、日常生活に支障が出るような痛みがある場合には、市販の抗炎症薬や湿布を取り入れることも検討されるようです。くすりの窓口では、セルフケアの一環として適切に使用する方法が紹介されています。ただし、長引く場合や強い痛みを伴う場合は自己判断せず、専門家のアドバイスを受けることが推奨されています。
#肩甲骨の痛み #セルフケア #ストレッチ習慣 #RICE療法 #生活改善
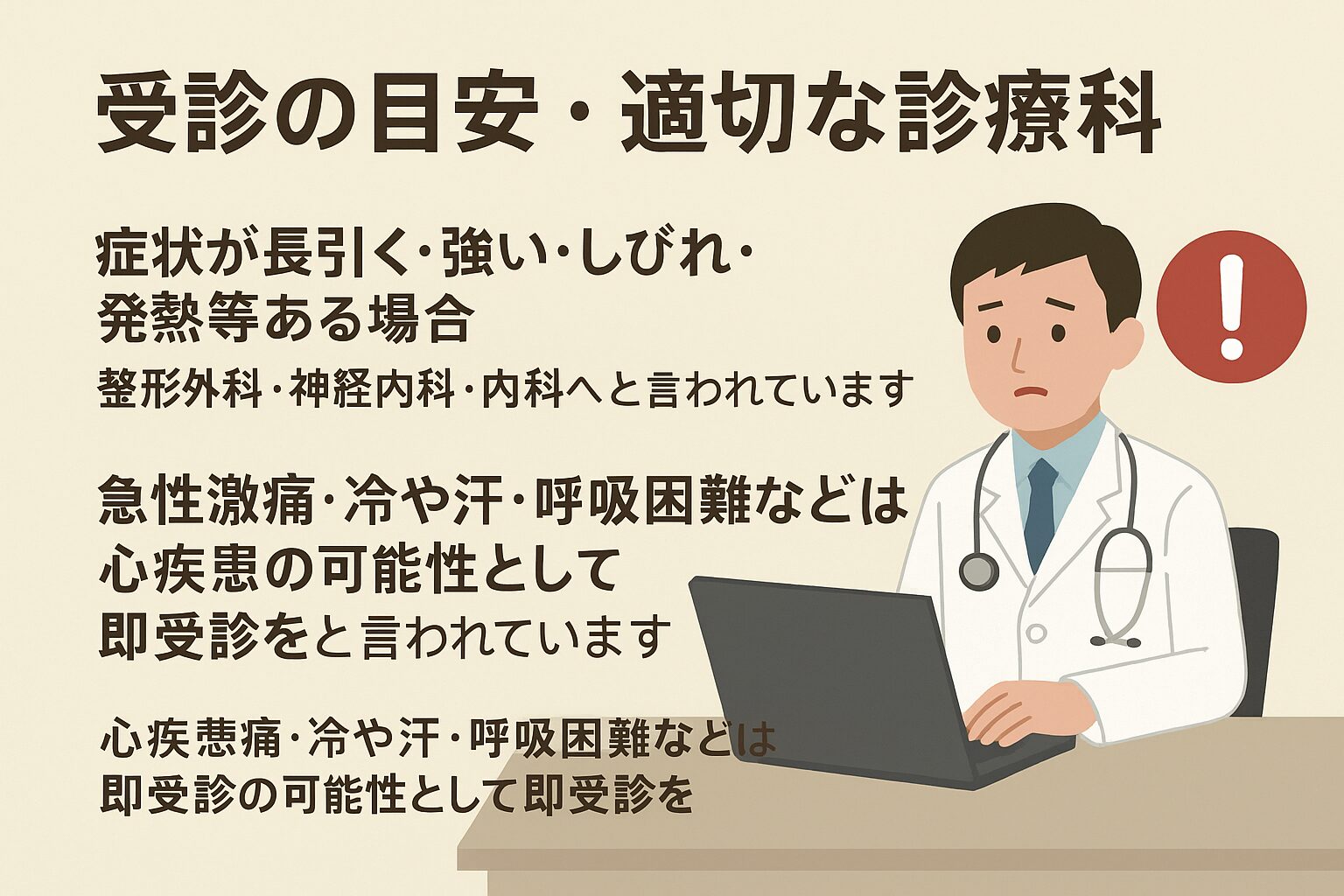
肩甲骨の真ん中が痛い状態が数日から数週間続く場合や、痛みが強くしびれを伴う時、さらに発熱がある時は注意が必要だと言われています。BLBはり灸整骨院の情報によると、こうしたケースでは自己判断で様子を見るよりも、整形外科や神経内科、内科での相談が推奨されているそうです(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/7085/)。
また、症状検索エンジン「ユビー」でも、痛みが慢性的に続く場合や他の症状を伴う場合は、専門的な検査が必要になる可能性があると示されています。
一方で「急に背中が強く痛んだ」「冷や汗が止まらない」「呼吸が苦しい」といった急性の症状は、心疾患に関連している可能性があると言われています。メディカルノートの解説でも、狭心症や心筋梗塞、大動脈解離などが背中の痛みとして現れるケースがあるとされ、こうした場合は救急外来を含めた早急な来院がすすめられています(引用元:https://medicalnote.jp/symptoms/肩甲骨が痛い)。
特に普段とは明らかに異なる強い痛みを感じた場合は、無理に我慢せず、できるだけ早めに医療機関を頼ることが重要だとされています。
#肩甲骨の痛み #受診目安 #整形外科 #心疾患の可能性 #早期相談

肩甲骨の真ん中の痛みは、人によって原因が異なるため「実際に改善がみられた症例」を知ると安心につながります。アールカイロプラクティックセンターの症例紹介では、40代女性が長年デスクワークによる肩甲骨の違和感に悩まされていたケースが掲載されています。姿勢や筋肉のバランスを整える施術を続けた結果、日常生活での負担が軽減し、痛みが和らいだと報告されています(引用元:https://www.aruchiro.com/)。このような具体例は「自分の症状も改善の糸口があるかもしれない」と感じられる要素になると言われています。
また、原因を理解するためには「文字だけでなく図やイラストを用いた解説」が効果的だと言われています。例えば、筋肉の緊張、神経の圧迫、関節の障害、内臓由来の関連痛といった原因をチャート化することで、読者が自分の症状を当てはめやすくなるとされています。アールカイロのサイトでも、症例に加えて分かりやすい図解を提示し、読み手が直感的に理解しやすい工夫が行われていました。
単なるセルフケアや一般論ではなく、実際の改善事例や専門家が示す資料を取り入れることで、記事全体の信頼度が高まると言われています。特に肩甲骨周辺の痛みは「放置してよいのか」「医療機関に行くべきか」という不安が伴いやすいため、症例紹介やチャートを交えることで安心感を与える効果があるようです。
#肩甲骨の痛み #症例紹介 #信頼性 #原因別チャート #改善例