- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30
- 最終受付時間19:00
- 定休日木・日・祝
兵庫県姫路市別所町北宿1046−3
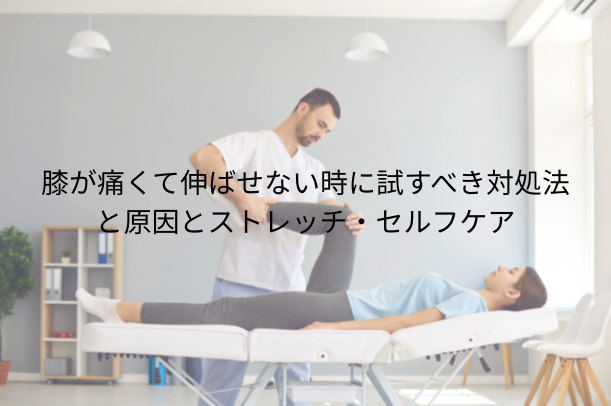
変形性膝関節症、半月板損傷、膝蓋下脂肪体炎、靭帯・軟骨の損傷など
各疾患の特徴と典型的な症状を簡潔に整理
痛みの場所やタイミング(伸ばす時、曲げるとき、ロッキングなど)
引っかかり感、腫れ、水が溜まる感覚などの特徴
安静・冷却(RICE処置)
痛みの悪化を避ける動作(正座・ジャンプなど)
膝周りの柔軟性向上:大腿四頭筋、ハムストリングス、腓腹筋など
理学療法士推奨の簡単リハビリトレーニング(3分程度)
専門医による問診、画像診断(レントゲン・MRI)、症状の継続やロッキングなどの緊急性の判断
保存療法から手術まで、症状に応じた選択肢紹介

「膝が痛くて伸ばせない…なんでこんなことに?」
日常生活の中でふと気づく違和感。そのまま放っておくと、歩行や立ち上がり動作にも影響が出てしまうことがあります。
膝が伸びない状態には、いくつかの代表的な原因があり、年齢や生活習慣によって異なる傾向があるとも言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1597/)。
加齢や長年の負担により膝の軟骨がすり減ることで、関節の隙間が狭くなり、膝の可動域が制限される状態です。特に中高年の女性に多く見られるとも報告されています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E2%80%8B%E8%86%9D%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%81%8F%E3%81%A6%E4%BC%B8%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%96%BE)。
膝のクッション役を果たす半月板が損傷すると、膝の動きが制限されることがあります。ロッキング(膝が途中で動かなくなる)や急な痛みを感じる場合は、この可能性も否定できません。スポーツをしている若い人にも発生しやすいとされています(引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/%E8%86%9D%E7%97%9B%E8%A7%A3%E6%94%BEblog/knee-not-straight)。
膝のお皿の下にある脂肪組織が炎症を起こすことで、膝を伸ばす動作で痛みが出やすくなります。特に膝を突いたり、曲げ伸ばしを繰り返す動作をする方に多い傾向があると言われています(引用元:https://www.medicalcare.or.jp/column/knee-pain/)。
前十字靭帯や膝窩筋腱(しっかきんけん)などが損傷している場合も、膝をまっすぐに伸ばしきれなくなることがあります。腫れや熱感、強い痛みが同時に出るケースもあるようです。
膝周囲の筋肉が固くなっている、あるいは過去のけがなどで組織が癒着していると、膝がスムーズに伸びにくくなることがあります。この場合は、筋肉を柔らかく保つストレッチや運動が有効とされています。
原因によって対処法も異なりますので、「ただの疲れかな」と軽視せず、自分の症状に合った対応を検討していくことが大切です。膝が伸びない、痛むという状況が続くときには、専門機関への相談も視野に入れてみてください。
#膝が伸ばせない原因
#変形性膝関節症
#半月板損傷
#膝蓋下脂肪体炎
#靭帯損傷と筋肉の硬さ

膝が伸ばせない、または痛むとき、その症状の出方によって原因や対応の方向性が異なると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1597/)。ここでは、自分でできる簡単なセルフチェックのポイントをご紹介します。あくまで目安であり、継続する症状は専門機関での確認が必要です。
膝をまっすぐにしようとした瞬間に鋭い痛みや突っ張り感がある場合、半月板や靭帯の損傷、膝蓋下脂肪体炎などの関与が考えられると言われています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E2%80%8B%E8%86%9D%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%81%8F%E3%81%A6%E4%BC%B8%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%96%BE)。
痛みの強さや持続時間、動かす角度によって変化するかも観察しましょう。
膝を動かしたときに「カクッ」と引っかかる感覚や、一定の角度で膝が止まってしまう状態は、半月板損傷や遊離体(関節内の骨や軟骨片)が原因のことがあるとされています(引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/%E8%86%9D%E7%97%9B%E8%A7%A3%E6%94%BEblog/knee-not-straight)。
無理に動かそうとすると痛みが悪化する場合があるため、慎重な動作を心がけることが大切です。
膝関節内の炎症や損傷が原因で、関節液が増えて腫れたり、水が溜まったように感じるケースもあります。変形性膝関節症や外傷後の炎症でも起こると言われています(引用元:https://www.medicalcare.or.jp/column/knee-pain/)。
膝を触って熱感がある場合は、炎症反応が進んでいる可能性もあるため注意が必要です。
階段の上り下りやしゃがみ動作で痛みが強まる場合、大腿四頭筋や膝蓋腱の関与が考えられることもあります。運動時だけ痛むのか、安静時も続くのかをチェックすることが参考になるとされています。
このように、膝の症状は出方によって原因の見当をつけやすくなると言われています。セルフチェックで気になる項目が複数当てはまる場合は、早めの相談が安心です。
#膝セルフチェック
#膝の伸びづらさ
#膝の痛みのパターン
#ロッキング症状
#膝の腫れと水溜まり

膝が伸ばせない、あるいは痛む状態に気づいたとき、「これって放っておいても大丈夫かな…?」と不安になることはありませんか?
無理に動かす前に、まずは体の声に耳を傾けることが大切だと言われています。ここでは、自宅で無理なく取り組める初期対応のセルフケア法をご紹介します(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1997/)。
膝に痛みや腫れがあるときは、まずはその部位を安静にすることが大前提とされています。無理に歩いたり、階段を上り下りするのは避け、なるべく膝を高くして寝かせる姿勢が楽だとされることもあるようです。
加えて、炎症が疑われる場合にはアイシングも有効と言われています。タオルで包んだ保冷剤を膝に10〜20分あて、30分ほど間隔をあけて繰り返す方法が一般的とされており、痛みの緩和や腫れの抑制につながる可能性があるようです(引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/%E8%86%9D%E7%97%9B%E8%A7%A3%E6%94%BEblog/knee-not-straight)。
痛みが和らいできたタイミングで、太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)を軽く伸ばすストレッチを取り入れると、関節の可動域を保ちやすくなると言われています。
ただし、痛みが強いときや無理な方向に動かすのは逆効果になる可能性もあるため、違和感がない範囲で行うことが望ましいとされています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch/)。
歩行時や外出時に不安がある場合、膝用サポーターや簡易的なテーピングを活用することで関節を安定させ、負担を軽減できる可能性があるとも言われています。
ただし、長時間使用することで血流が妨げられるリスクもあるため、適切なサイズと着用時間を守ることが勧められています(引用元:https://www.ashiya-uedacl.com/knee_hurts/)。
膝のセルフケアは「無理せず」「こまめに」「自分に合った方法で」が基本です。改善が見られない、または悪化していると感じた場合は、専門機関への相談を早めに検討することも選択肢の一つと言われています。
#膝のセルフケア
#膝が伸ばせない
#アイシングと安静
#軽いストレッチ
#サポーター活用法

「膝の痛みで動かすのが怖い…」そんなときこそ、正しい知識で体を動かすことが大切だと言われています。膝を支える筋肉をしっかり働かせることで、関節の負担を軽くしやすくなるとされており、軽めのストレッチや筋トレは、自宅でできるケアのひとつです(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch/)。
痛みが強いときは避けるべきですが、落ち着いてきたら徐々にストレッチを取り入れてみるのがよいとも言われています。
太ももの裏側を伸ばすことで、膝の曲げ伸ばしがスムーズになる可能性があります。
・椅子に座ったまま、片足を前に伸ばし、つま先に向かって軽く前屈する
・背筋を伸ばし、反動をつけずにゆっくり伸ばすのがポイント
前ももをやさしく伸ばすことで、膝のお皿周囲の動きがなめらかになりやすいとされています。
・横向きに寝転がり、上側の足の足首を持ってかかとをお尻に引き寄せる
・反対の手で体を支えることで安定します
(参考元:https://tokyo-seikeigeka.jp/%E8%86%9D%E7%97%9B%E8%A7%A3%E6%94%BEblog/knee-not-straight)
ストレッチと並行して行いたいのが、膝周りの筋力を支えるトレーニングです。特に、太ももやお尻まわりの筋肉を鍛えることが推奨されているようです。
・【セッティング】
仰向けに寝て、膝の裏にタオルを丸めて置き、軽く押しつける
→ 太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)を意識
・【レッグレイズ】
仰向けの状態で片脚を伸ばしたまま、10〜15cm持ち上げて5秒キープ
→ 負荷は軽めでも継続することが大切とされています
(参考元:https://www.bjd-jp.org/archives/column/2715)
あくまで無理のない範囲で、「ちょっと伸びて気持ちいいな」と感じるくらいの強度が目安だと言われています。日々の習慣に少しずつ取り入れて、膝まわりのサポート力を高めていきましょう。
#膝ストレッチ
#筋力トレーニング
#大腿四頭筋
#ハムストリングス
#膝のセルフケア

「セルフケアを続けてるのに、なかなか良くならないな…」
そんなふうに感じたときは、一度専門機関でのチェックを受けるのが安心とも言われています。
例えば、以下のような症状が続いている場合は、整形外科への来院が選択肢になるとされています。
安静にしても痛みが引かない
膝がまっすぐ伸びず、違和感が強まっている
関節が腫れて熱感がある、または水がたまっている感覚がある
歩行や階段の昇降が困難なほどの痛みがある
動かすと「ガクッ」と引っかかる感じがある
いずれも、関節内の構造に何らかの問題が生じている可能性があるとされており、放置することで慢性化のリスクが指摘されることもあります(引用元:https://www.ashiya-uedacl.com/knee_hurts/)。
整形外科では、まず問診や触診で症状の程度や経過を丁寧に確認し、必要に応じて画像検査(レントゲン・MRIなど)を行うことが一般的とされています(引用元:https://www.nishiarai-seikei.com/knee_pain/)。
検査の内容としては以下のようなものがあるようです。
レントゲン:骨の変形や隙間の確認
MRI:半月板や靭帯、軟骨などの損傷状況の把握
関節液の確認:腫れや炎症の程度を調べるための穿刺が行われる場合も
その上で、痛みの原因に合わせて施術方針が提案される流れになります。初期段階では、薬の処方や物理療法(温熱・電気刺激)、理学療法士による運動指導など、保存的な対応が多くなることがあるとされています(引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/)。
膝の痛みや可動域の問題は、早めに対応することで日常生活への影響を抑えやすくなると言われています。心配が続く場合には、専門の医師に相談してみることもひとつの選択肢と考えられます。
#膝の痛みが続く場合
#整形外科での検査
#レントゲンとMRI
#膝の違和感の相談目安
#施術の流れと内容