#生理痛
#鍼灸
#ツボ
#施術の流れ
#通院頻度
- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30
- 最終受付時間19:00
- 定休日木・日・祝
〒671-0223
兵庫県姫路市別所町北宿1046−3
兵庫県姫路市別所町北宿1046−3
駐車場あり(5台)
地図を見る
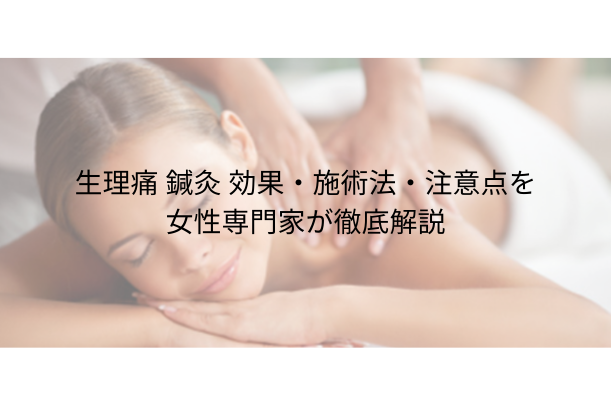
– 西洋医学的なアプローチ(血流改善、プロスタグランジン調整、神経伝達抑制、自律神経調整)
– 東洋医学・鍼灸理論での解釈(気血の滞り、腎・肝・脾の関係、冷え・お血など)
– 専門家・研究例の紹介(文献紹介があれば)
– 初回カウンセリング・体質チェックの手順
– 施術の流れ(仰向け/うつ伏せ、鍼/お灸/手技の併用など)
– よく使われるツボとその効能(例:三陰交、関元、中極、照海など)
– 通院頻度と期間の目安(初期段階 → 維持期)
– どの時期に施術を行うと効果が出やすいか(生理前、生理中など)
– 鍼灸のメリット(副作用が少ない、自然な方法、体質改善型)
– 注意点・禁忌(出血傾向、過度な刺激、皮膚状態、妊娠中・生理中の配慮など)
– 施術中・施術後に感じることがある一時的な反応(だるさ、出血増加、痛み増加など)
– 質の高い鍼灸院を選ぶポイント(衛生、国家資格、女性施術者、口コミなど)
– 冷え対策(入浴、腹巻、足湯など)
– 適度な運動・ストレッチ(骨盤周りをほぐす、軽い有酸素運動など)
– 食事・栄養アプローチ(血行促進、抗炎症作用のある食材など)
– 睡眠・ストレス管理
– 漢方・東洋医学の補助的活用(あれば簡単に紹介)
– 鍼灸を受けて改善した人の体験談(ビフォー・アフター、具体的な変化)
– よくある質問と回答 (例:生理中でも受けられるか?痛みはあるか?保険は適用されるか?どれくらいで効果が出るか?)
– トラブル時の対処法(不調が出たときはどうするか)

生理痛が起こる一因として、子宮内膜から分泌されるプロスタグランジンという物質の作用が知られています。この物質は子宮の収縮を強め、血流の停滞や痛みの増加につながると言われています。鍼灸は血管を広げて血流を改善し、酸素や栄養を子宮周辺に運びやすくする作用があるとされます。また、神経を介した痛みの伝達を抑える効果や、自律神経のバランスを整える作用が期待されており、交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズにすることで、体の緊張を和らげやすいと考えられています。引用元:きりん堂鍼灸接骨院(https://ogikubo-kirindou.com/blog/blog-6051/)
一方で、東洋医学では生理痛は「気血の滞り」や「冷え」、「腎・肝・脾の働きの不調」によって起こると説明されています。血の巡りが悪くなると「お血」と呼ばれる状態が生じ、下腹部の重だるさや痛みとして現れやすいとされています。鍼灸はツボを刺激することで気と血の流れをスムーズにし、体を温め、内臓の働きを整える効果が期待されていると言われています。引用元:明治国際医療大学(https://www.meiji-u.ac.jp/)/赤岩治療院(https://akaiwa89-ganseihirou.com/blog/shikyusenkinsyou-chiryou/)
研究の中には、生理痛に対して鍼灸施術を行ったグループが、鎮痛薬のみを使用したグループに比べて痛みのスコアが低下したという報告もあります。また、定期的に施術を続けることで血流の改善やホルモンバランスの安定につながる可能性が示唆されています。これらはあくまで「有効なケースがある」とされるものであり、すべての人に同じ効果があるわけではありません。ただし、西洋医学的な視点と東洋医学的な視点が補い合う形で説明できるのは鍼灸ならではの特徴とも言えます。
#生理痛
#鍼灸
#血流改善
#東洋医学
#自律神経調整

生理痛で鍼灸を希望する場合、まず行われるのがカウンセリングです。ここでは痛みの程度や周期、生活習慣などを細かく確認し、触診によって体の冷えや張りの状態をチェックすることが多いと言われています。こうした情報をもとに、その人の体質に合わせた施術プランが立てられるのが特徴です。引用元:たくろう鍼灸院(https://takuro-shinkyu.com/useful/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%97%9B%E3%81%AB%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E9%8D%BC%E7%81%B8%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%EF%BD%9C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E6%B3%A8/)
施術は、仰向けと俯せを使い分けながら鍼やお灸を組み合わせて行われることが一般的です。下腹部や腰周りを中心に、症状に応じて手足のツボにもアプローチしていくと言われています。痛みの強い部位だけでなく全身のバランスを意識し、体の巡りを整えることが重視されています。必要に応じて手技や温熱療法を併用するケースもあるようです。引用元:chitose-karasuyama.com(https://chitose-karasuyama.com/acupuncture/seirituu.html)
生理痛の施術で頻繁に使われる代表的なツボには以下のようなものがあります。
三陰交(さんいんこう):足首の内側にあり、血流を促し冷えの改善に役立つとされる
関元(かんげん)・中極(ちゅうきょく):下腹部に位置し、子宮や膀胱周囲の働きを整えるとされる
照海(しょうかい):足首内側のくぼみにあり、ホルモンバランスの調整を助けるといわれる
これらのツボは古くから婦人科系の不調に用いられてきたとされ、血行促進や冷えの改善を目的に活用されています。引用元:sumiyoshi-shinkyu.com(https://sumiyoshi-shinkyu.com/225523)
施術の頻度は体の状態や症状の重さによって異なりますが、初期段階では週に1〜2回、その後は症状が落ち着けば月1回程度のメンテナンスに移行するケースが多いと言われています。定期的に通うことで体質の改善につながりやすいとされ、長期的なサポートとして取り入れる方もいます。
生理痛に対しては、生理中に限らず「生理前の1週間」から施術を始めると体の緊張を和らげやすいとされます。生理後の時期も巡りを整える良いタイミングといわれ、周期全体を意識して施術を組み立てることで持続的な効果が期待できるとされています。

鍼灸は薬を使わないため副作用が少なく、体にやさしい自然なアプローチとされています。体質に合わせた施術ができることから、冷えや血行不良、自律神経の乱れといった要因を整える効果が期待されていると言われています。また、定期的に続けることで全身のバランスを取りやすくなり、根本的な改善を目指す方法として注目されています。引用元:たくろう鍼灸院(https://takuro-shinkyu.com/useful/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%97%9B%E3%81%AB%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E9%8D%BC%E7%81%B8%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%EF%BD%9C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E6%B3%A8/)
一方で、誰にでも安全というわけではなく、いくつかの注意点があります。出血しやすい体質や抗凝固薬を使用している場合は、施術の刺激によって内出血が起こりやすいと言われています。また、皮膚の炎症や感染がある部位への施術は避けられることが一般的です。妊娠中や生理中の施術についても、体調や症状に合わせた調整が必要とされ、専門家と相談することが望ましいとされています。引用元:sumiyoshi-shinkyu.com(https://sumiyoshi-shinkyu.com/225523)
鍼灸を受けた直後には、一時的にだるさを感じたり、施術部位に赤みや軽い痛みが出る場合もあります。人によっては一時的に経血量が増えると感じるケースもあると言われていますが、多くは数時間から数日で落ち着く反応とされています。こうした体の変化は「好転反応」とも呼ばれ、体が回復に向かう過程と説明されることがあります。ただし強い痛みや体調不良が続く場合は、速やかに専門家へ相談することが大切です。引用元:chitose-karasuyama.com(https://chitose-karasuyama.com/acupuncture/seirituu.html)
安心して施術を受けるには、鍼灸師が国家資格を持っているかどうかを確認することが重要です。使い捨て鍼を用いた衛生管理、施術前の丁寧な説明、施術後のフォローなどが整っている鍼灸院は信頼性が高いとされています。女性施術者が在籍しているかどうかや、口コミでの評価を参考にするのも選び方の一つです。施術環境が清潔であることも安心につながるポイントです。

生理痛が強くなる背景には「冷え」が関わっているとよく言われています。お風呂にゆっくり浸かって体を芯から温めたり、腹巻やカイロを活用して下腹部や腰を温めることが有効だとされています。特に足先は冷えやすいため、足湯を習慣にするのも良い工夫とされています。こうした温めるケアは鍼灸の効果を助け、血流改善を持続させやすいと説明されています。引用元:sumiyoshi-shinkyu.com(https://sumiyoshi-shinkyu.com/225523)
骨盤周りをほぐすストレッチや軽い有酸素運動は、血流を促し筋肉のこわばりを和らげると言われています。例えばヨガの骨盤調整ポーズや、ウォーキングなどの全身運動はおすすめされやすい方法です。体を動かすことで気分転換にもなり、ストレスの軽減にもつながると考えられています。引用元:たくろう鍼灸院(https://takuro-shinkyu.com/useful/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%97%9B%E3%81%AB%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E9%8D%BC%E7%81%B8%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%EF%BD%9C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E6%B3%A8/)
普段の食事でも体の巡りに影響を与えると言われています。血行促進に役立つ鉄分やビタミンE、抗炎症作用があるとされるオメガ3脂肪酸を含む食品(青魚、ナッツ類など)を意識すると良いとされています。甘い物やカフェインの取りすぎは痛みを強める可能性があると指摘されているため、バランスの良い食事が推奨されます。引用元:chitose-karasuyama.com(https://chitose-karasuyama.com/acupuncture/seirituu.html)
睡眠不足やストレスは自律神経の乱れを招き、生理痛を悪化させる要因になることがあるとされています。質の良い睡眠を確保し、リラックスできる時間を持つことが大切です。深呼吸やアロマなどのリラクゼーション法を取り入れるのも有効だと紹介されています。
鍼灸と同じく東洋医学の一環として、漢方薬が体質改善に役立つと考えられる場合もあります。たとえば冷えやお血の状態に応じた漢方が提案されることがあり、鍼灸と組み合わせることでより効果を高めやすいとされています。ただし服用にあたっては必ず専門家に相談することが望ましいです。
#生理痛
#鍼灸
#セルフケア
#生活習慣改善
#冷え対策

鍼灸を取り入れたことで、生理痛がやわらいだと感じる方もいると言われています。例えば「以前は鎮痛薬が手放せなかったけれど、数回の施術で服用回数が減った」「下腹部の重さが軽くなり、仕事中も集中しやすくなった」といった声が挙げられています。ある方は、鍼灸に通い始めてから冷えが改善し、周期も安定してきたと感じているそうです。このように、ビフォー・アフターを実感できるケースがあると紹介されています。ただし効果の程度や期間には個人差があり、必ずしも同じような結果になるわけではないと説明されています。引用元:たくろう鍼灸院(https://takuro-shinkyu.com/useful/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%97%9B%E3%81%AB%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E9%8D%BC%E7%81%B8%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%EF%BD%9C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E6%B3%A8/)
生理中でも受けられる?
生理中でも鍼灸は可能とされており、痛みを和らげる目的で施術を行う方もいると言われています。ただし体調によって刺激を弱めるなどの調整が必要になるケースもあるため、事前に相談するのが安心です。引用元:sumiyoshi-shinkyu.com(https://sumiyoshi-shinkyu.com/225523)
施術は痛い?
鍼は髪の毛ほどの細さで、ほとんど痛みを感じにくいと説明されています。刺入時にチクッとすることもありますが、多くは「思ったよりも楽だった」という声が多いようです。
保険は使える?
健康保険が使えるのは限られた疾患に対してで、生理痛に関しては自費になるケースが多いと言われています。
どれくらいで効果を感じられる?
1回目から楽になる人もいれば、数回通って体質改善を実感する人もいます。短期的な効果と長期的なケアの両面があるため、継続的に受けることが望ましいとされています。引用元:chitose-karasuyama.com(https://chitose-karasuyama.com/acupuncture/seirituu.html)
施術後にだるさや眠気が出るのは「好転反応」と呼ばれる一時的な変化だと説明されることがあります。ただし強い痛みや発熱、体調不良が続くときは自己判断せず、必ず施術者や医療機関に相談することが推奨されています。信頼できる鍼灸院を選ぶことが、こうしたトラブルを避けるための第一歩とも言われています。
#生理痛
#鍼灸
#体験談
#FAQ
#トラブル対処