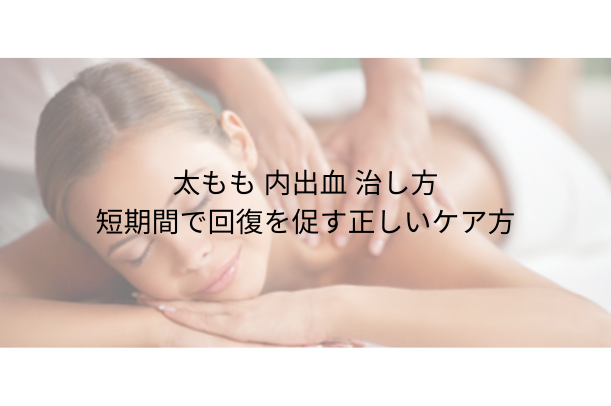1.股関節の痛みの原因を理解する
‑ 腸腰筋炎/腸腰筋など筋肉の炎症や硬さ
‑ 股関節インピンジメント(FAI:骨同士の衝突)
‑ 変形性股関節症、鼠径部痛症候群(グロインペイン)
‑ 骨盤のゆがみや腰由来の関連痛
→ 初心者~中高年ランナーまでカバー
2.**走り方(フォーム)と習慣の見直し**
‑ ヒールストライク/片脚に体重偏重などのNGフォーム
‑ 骨盤の傾き・身体の左右ブレ改善
‑ ランニング頻度・距離の見直し(オーバーユース対応)
3.ストレッチと筋力トレーニングで柔軟性と安定性を高める
‑ 腸腰筋、大腿四頭筋、内転筋、中臀筋などのストレッチ
‑ クラムシェル、ヒップリフト、体幹トレ(プランク・バードドッグなど)
4.痛み発生時のセルフケアと休養のポイント
‑ 痛みが出た直後はジョギング中止・アイシング(冷却)と休息
‑ 故障の急性期を越えたら軽めウォーキングや低衝撃ランニングで継続も検討
5.整形外科や専門家による診断・治療が必要なサイン
‑ 痛みが長引く/関節の引っかかりや異音/片脚で体重かけられない etc.
‑ 変形性股関節症、関節唇損傷、腰由来の関連痛などの可能性
‑ 医師や専門家による検査(MRIなど)と適切な施術・再発予防の提案
1.股関節の痛みの原因を理解する
股関節の構造と痛みの仕組み
「ジョギングしてたら、股関節のあたりがズキッと痛むんだけど…これって大丈夫かな?」
こんなふうに感じたこと、ありませんか?実は、股関節の痛みっていろんな原因があるんです。ただの筋肉痛と思って軽く見てしまうと、長引くこともあるので注意が必要です。
股関節は、体の中でもっとも大きな関節のひとつで、上半身と下半身をつなぐ重要なパーツです。しかも、走ったり歩いたりするたびに体重の何倍もの負荷がかかっているんですって。だからこそ、ちょっとしたズレや使いすぎが痛みに変わることもあると言われています(引用元:熊の実整骨院)。
よくある原因①:筋肉の硬さや疲労
まず多いのが、筋肉の柔軟性が足りていないケース。特に腸腰筋(ちょうようきん)や大腿四頭筋(だいたいしとうきん)が硬くなると、股関節の動きが制限されて負担が集中してしまうそうです。
さらに、ジョギングを始めたばかりの人や久しぶりに走った人の場合、筋肉が疲労しやすく、炎症が起きやすい傾向があると言われています(引用元:宮川整骨院)。
よくある原因②:股関節インピンジメント(FAI)
少し専門的な話ですが、「FAI(大腿骨寛骨臼インピンジメント)」という症状もあります。これは骨の形状に問題があって、動かしたときに骨同士がぶつかりやすくなる状態なんですね。このぶつかりが繰り返されると、関節の中で炎症が起きる可能性があるとされています(引用元:阿部整形外科)。
よくある原因③:体のゆがみやフォームの崩れ
走るフォームにも原因があること、意外と多いです。例えば片足重心になっていたり、骨盤が前に傾いていたりすると、左右の股関節にかかる負担が変わってきます。これが積み重なることで、痛みに変化していくケースもあると考えられています。
「え、そんなことで?」と思うかもしれませんが、実際に整骨院ではそういったケースも多いとのことです。
#股関節の痛み #ジョギング初心者 #股関節インピンジメント #筋肉の硬さ #走り方改善
2.走り方(フォーム)と習慣の見直し
3.ストレッチと筋力トレーニングで柔軟性と安定性を高める
4.痛み発生時のセルフケアと休養のポイント
5.整形外科や専門家による診断・検査が必要なサイン
痛みを放置してはいけないケースとは?
「走ってたら股関節が痛んだ。でも、まぁそのうち楽になるでしょ」
…とつい思ってしまう気持ち、わかります。でも実は、その“そのうち”が意外と厄介なこともあるんです。
たとえば、痛みが1週間以上続いている場合や、日常生活にも支障が出ているケースでは、専門家によるチェックが必要だと考えられています(引用元:にっこり鍼灸整骨院)。特に、片脚に体重を乗せたときに股関節がズキンとする、階段の上り下りがつらい、歩き方が明らかに変わってきた…こういった症状は放置しない方がよいとも言われています。
また、股関節からパキッという音が頻繁にする、股関節の動かせる範囲が狭くなった気がするといった感覚も、何らかの異常があるサインの可能性があると考えられているようです(引用元:熊の実整骨院)。
医療機関への来院を考えるタイミング
「じゃあ、どのタイミングで整形外科に行くべき?」
そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。
ひとつの目安として、「休んでも改善がみられない場合」や「安静時でも痛みが出ているとき」が挙げられています(引用元:阿部整形外科)。さらに、股関節に腫れや熱感がある場合、夜間に痛みで目が覚めるといった症状も、炎症や損傷の可能性があるとされており、早めに医師の判断を仰ぐことが望ましいと考えられています。
医療機関では、必要に応じてレントゲンやMRIといった検査を行い、痛みの原因を特定する流れになることが多いそうです。適切な施術方針を立てるためにも、早めの相談が大切だとされています。
「これくらい大丈夫」と思わずに、自分の体の声にちゃんと耳を傾けてあげてくださいね。
#股関節の痛み持続 #整形外科の受診目安 #専門家の触診 #股関節の異音 #慢性痛チェック
この記事をシェアする
関連記事