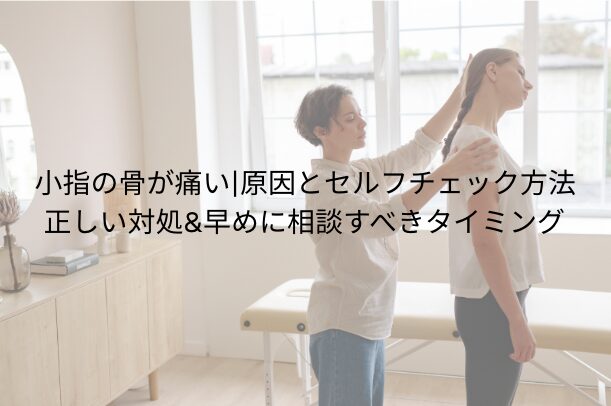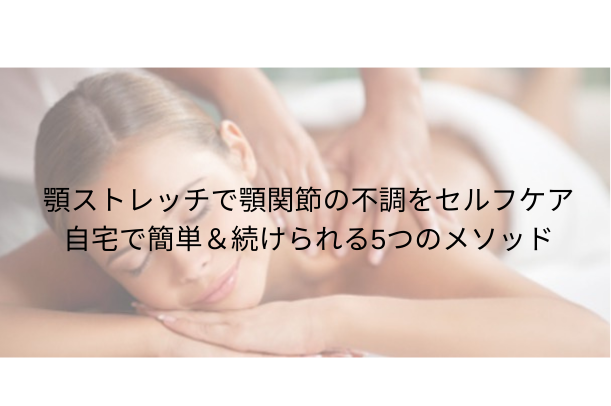1.膝が痛い時に“まず行くべき病院”とは
受診すべき科(整形外科が基本) → 「膝 痛い」相談のうち49%が整形外科受診を勧められているデータあり。
専門病院・クリニック(膝関節症などに特化)紹介例
緊急受診が必要なサイン(歩けない/腫れ・発熱ありなど)
2.膝の痛み:病院で診てもらう前に知っておきたい原因と症状
痛む部位別の原因(内側・外側・前・皿下)
代表的な疾患(変形性膝関節症/半月板損傷/靭帯損傷など)
放置するとどうなるか(進行・重症化のリスク)
3.病院での診察・検査・治療の流れ
問診・触診・画像検査(レントゲン・MRI)
保存療法(薬・注射・リハビリ)と手術療法(人工関節など)
専門病院が強みとする治療(再生医療・関節鏡など)紹介
4.膝が痛い時に“病院を選ぶ”ためのチェックポイント
医師・専門領域の確認(膝関節専門医の有無)
検査設備・リハビリ施設・通院環境(立地・駐車場など)
費用・保険適用・自費治療の有無(特に特殊治療の場合)
口コミ・症例実績・患者の声(選ぶ際の参考)
5.病院に行く前・行った後にできる膝ケア&再発予防
受診前にしておきたいセルフチェック・痛み軽減法(体重管理・姿勢改善など)
受診後に続けたいリハビリ・運動療法(膝周囲筋力強化など)
日常生活で膝に負担をかけない工夫(座り方・歩き方・荷重分散)
再発・進行を防ぐための定期チェック・生活習慣改善
1.膝が痛い時に“まず行くべき病院”とは

「膝が痛い」と感じたとき、どこへ行けばいいのか迷う方は少なくありません。実際、症状によって行くべき病院が変わることもありますが、一般的には整形外科が第一の選択肢とされています。膝関節や骨、筋肉、靭帯のトラブルを専門的に扱う診療科であり、画像検査やリハビリの設備も整っているケースが多いからです。
また、症状検索エンジン「ユビー(Ubie)」によると、「膝が痛い」と入力したユーザーのうち約49%が整形外科での来院をすすめられていると言われています(引用元:https://ubie.app/)。同様に、病院ナビなどの医療情報サイトでも、**「膝の痛み=整形外科」**という判断が一般的です(引用元:https://byoinnavi.jp/)。
ただし、「痛みが軽い」「違和感が出たり引いたりする」場合は、まず近所のクリニックで相談しても問題ないとされています。医師の触診を受け、必要であれば専門的な検査ができる病院を紹介してもらう流れが安心です。
受診すべき科(整形外科が基本)
膝の痛みは、関節や筋肉の炎症、骨の変形、靭帯損傷など、複数の要因が絡むことがあります。そのため、まずは整形外科で原因を見極めることが重要です。整形外科では、X線やMRIを用いた画像検査、必要に応じてリハビリテーションや物理療法を行うケースもあります。
また、「膝が腫れている」「階段の上り下りがつらい」「動かすと音が鳴る」といった症状も整形外科で対応可能です。医師の触診を受け、場合によってはスポーツ整形や関節外科などの専門外来を紹介されることもあります(引用元:https://ubie.app/、https://byoinnavi.jp/)。
専門病院・クリニック(膝関節症などに特化)紹介例
近年では、膝関節疾患に特化した専門クリニックも増えています。たとえば「変形性膝関節症」「半月板損傷」「靭帯再建」など、症状に応じた検査・施術を行う施設です。
関節鏡を用いた低侵襲な検査や、再生医療を取り入れる病院も登場しており、より精密な評価や個別対応が可能になっていると言われています(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/)。
こうした専門施設は、整形外科の中でも「膝関節センター」「スポーツ整形外科」などの名称で設置されていることが多いです。症状が長引いている方や、以前別の病院で改善しづらかった方は、一度相談してみるとよいでしょう。
緊急受診が必要なサイン(歩けない/腫れ・発熱ありなど)
「少し痛い」だけであれば様子を見てもよい場合もありますが、次のようなサインがあるときは早めの来院が必要とされています。
-
歩けないほど強い痛みがある
-
急に膝が腫れた
-
熱をもっている、または発熱がある
-
怪我や転倒のあとから痛みが続く
これらは炎症や感染、骨折などの可能性があり、放置すると悪化する恐れがあります。イノルト整形外科では「歩けない・熱感・腫脹がある場合は早期検査が重要」と説明されています(引用元:https://inoruto.or.jp/)。
少しでも不安があるときは、我慢せず医師に相談することが大切です。早めの受診が、長引く痛みや将来的な関節変形を防ぐことにつながるとも言われています。
#膝痛 #整形外科 #膝関節症 #病院選び #膝の腫れ
2.膝の痛み:病院で診てもらう前に知っておきたい原因と症状

「膝が痛いけど、どんな原因があるの?」「病院に行く前に少しでも知っておきたい」と感じる方は多いと思います。膝の痛みといっても、痛む場所やきっかけによって原因はさまざまです。
ここでは、部位別の原因や代表的な疾患、そして放置によるリスクを整理して紹介します。受診前に目を通しておくことで、医師への説明や質問がスムーズになります。
痛む部位別の原因(内側・外側・前・皿下)
膝のどこが痛むかによって、原因のおおよその見当がつく場合があります。
-
膝の内側:中高年の方に多く、変形性膝関節症による軟骨のすり減りが関係すると言われています。歩行時や階段の昇り降りで痛みが強くなることが特徴です。
-
膝の外側:ランニングなどの繰り返し動作による外側側副靭帯や腸脛靭帯の炎症が原因のことがあります。スポーツ愛好家や若い世代にも見られます。
-
膝のお皿の下(膝蓋靭帯部):ジャンプや屈伸を繰り返すことで炎症が起きやすく、「ジャンパー膝」と呼ばれることもあります。
-
膝の前側:筋力バランスの崩れや姿勢、体重負担が影響して痛みを感じることもあります。
これらはあくまで一般的な傾向であり、正確な判断には専門医の触診や画像検査が必要です(引用元:ひざ関節症クリニック|医療法人社団活寿会 https://www.kneeclinic.jp/)。
代表的な疾患(変形性膝関節症/半月板損傷/靭帯損傷など)
膝の痛みの背景には、複数の疾患が関係していることがあります。
代表的なものとして、まず挙げられるのが変形性膝関節症です。加齢や過度な負担によって軟骨がすり減り、関節の動きに違和感や痛みが出るとされています。特に女性や肥満傾向の方に多い傾向があると言われています。
次に、半月板損傷。膝をひねったり、スポーツ中の衝撃によって起こることが多く、痛みとともに「引っかかる」「動かしづらい」と感じる方もいます。
そして靭帯損傷は、転倒や急な方向転換などがきっかけになることがあります。膝がぐらつくような感覚が特徴的です。
これらの疾患は早期発見・早期対応が大切で、放置すると慢性的な痛みや変形につながる可能性も指摘されています(引用元:足立慶友整形外科 https://clinic.adachikeiyu.com/)。
放置するとどうなるか(進行・重症化のリスク)
「痛いけど我慢できるから」と放置してしまうと、膝関節の変形や炎症が進み、歩行に支障をきたす場合があります。
特に変形性膝関節症は、初期の段階では軽度の違和感やこわばり程度ですが、進行すると階段の上り下りが難しくなり、正座やしゃがみ込みができなくなるケースもあるといわれています。
また、炎症や損傷を放置することで、膝周囲の筋肉が衰え、関節への負担がさらに増えるという悪循環も生まれやすくなります。
「少しでもおかしい」と感じた時点で、整形外科などの専門医に相談することが早期改善につながると言われています(引用元:公益社団法人 日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/)。
#膝痛 #変形性膝関節症 #半月板損傷 #靭帯損傷 #膝の原因
3.病院での診察・検査・治療の流れ

膝の痛みで病院を訪れると、「何をされるのか不安」と感じる方は多いのではないでしょうか。
整形外科などでは、症状の原因を特定し、最適な検査や施術方針を決めるために段階的な流れで診察が行われます。ここでは、一般的な問診から検査、治療までの流れをわかりやすく紹介します。
問診・触診・画像検査(レントゲン・MRI)
まず最初に行われるのが問診です。
「いつから痛いのか」「どの動作で痛むのか」「どんなきっかけで痛みが出たのか」などを細かく聞き取ることで、痛みのタイプを把握します。次に、医師が膝を実際に動かしながら行う触診。膝の腫れ、熱感、可動域などを確認し、炎症や損傷の有無を判断していきます。
必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査も行われます。
レントゲンでは骨の状態を、MRIでは軟骨・靭帯・半月板などの軟部組織を確認できるため、より詳細な分析が可能です。
この一連の流れによって、痛みの原因を特定しやすくなると言われています(引用元:https://ehiza.jp/)。
保存療法(薬・注射・リハビリ)と手術療法(人工関節など)
検査結果をもとに、医師は保存療法か手術療法のどちらを選択するかを提案します。
保存療法では、痛み止めや湿布などの薬の使用、ヒアルロン酸注射による関節の潤滑サポート、さらにリハビリテーションによる筋力改善などが中心です。これらは、症状を緩和し再発を防ぐことを目的に行われます。
一方、関節の変形や軟骨のすり減りが進行している場合には、手術療法が検討されます。
代表的なのは「人工膝関節置換術」で、変形性膝関節症の重度な症状に用いられるケースがあります。
ただし、すべての患者に必要なわけではなく、痛みや生活の支障度に応じて医師と相談のうえで判断されることが多いです(引用元:https://hospital.japanpost.jp/tokyo/shinryo/seikei/oa.html)。
専門病院が強みとする治療(再生医療・関節鏡など)紹介
最近では、専門病院が独自に行っている再生医療や関節鏡手術といった高度な治療法にも注目が集まっています。
再生医療では、自身の血液や細胞から抽出した成分を膝関節に注入し、組織の修復を促す施術が行われていると言われています。
また、関節鏡手術は小さなカメラを膝に挿入して内部を確認しながら行う低侵襲手術で、入院期間の短縮が期待できるとされています。
こうした新しい技術を積極的に取り入れているのが、「ひざの再生医療専門クリニック」や「関節鏡センター」などの施設です。
横浜ひざ関節クリニックでは、保存療法から再生医療まで幅広い選択肢を用意し、個々の症状に合わせた施術を提案しているとのことです(引用元:https://knee-yokohama.com/)。
#膝痛 #整形外科 #MRI検査 #人工関節 #再生医療
4.膝が痛い時に“病院を選ぶ”ためのチェックポイント

膝の痛みが続くと、「どの病院に行けばいいのかわからない」と悩む方は多いものです。整形外科といっても、病院ごとに得意分野や設備が異なります。ここでは、失敗しない病院選びのための4つのポイントを紹介します。
医師・専門領域の確認(膝関節専門医の有無)
まずチェックしたいのが、医師の専門領域です。
膝の痛みは、骨・靭帯・筋肉・軟骨など、複数の組織が関わるため、一般整形外科よりも「膝関節専門医」や「スポーツ整形外科」の経験がある医師がいる病院がおすすめと言われています。
足立慶友整形外科のように、膝関節疾患の手術・リハビリ・再生医療を総合的に扱う施設では、個々の症状に合わせた検査や施術方針を提案してもらえるとされています。
医師の経歴や得意分野は、公式サイトや病院案内で確認できることが多いので、来院前にチェックしておくと安心です。
(引用元:足立慶友整形外科 https://clinic.adachikeiyu.com/)
検査設備・リハビリ施設・通院環境(立地・駐車場など)
次に見るべきは、設備と通いやすさです。
精密な検査を行うには、レントゲンやMRIなどの画像機器が整っていることが重要です。加えて、慢性的な膝痛ではリハビリが欠かせないため、運動療法や物理療法が受けられるリハビリ施設があるかも確認しておきましょう。
また、通院が長期にわたる場合は「駅からの距離」「駐車場の有無」「バリアフリー対応」なども大切なポイントです。
足立慶友整形外科では、MRIや骨密度測定装置などの設備を備え、患者が通いやすい環境づくりを意識していると紹介されています。
(引用元:足立慶友整形外科 https://clinic.adachikeiyu.com/)
費用・保険適用・自費治療の有無(特に特殊治療の場合)
近年、再生医療やPRP(多血小板血漿)などの自費診療を取り入れる病院も増えています。
保険が適用される検査や施術、自由診療となる特殊施術など、料金体系を事前に確認しておくことが大切です。
初回カウンセリングや検査費、注射・リハビリなどの費用を公式サイトで明示している病院は信頼性が高い傾向があります。
また、「保険診療と併用できるのか」「分割払いに対応しているか」といった点も、通院を続ける上での判断材料になります。
口コミ・症例実績・患者の声(選ぶ際の参考)
最後に、口コミや実績も参考になります。
「スタッフの対応」「説明のわかりやすさ」「待ち時間」「施術後のフォロー」など、患者のリアルな声を確認することで、病院の雰囲気を把握しやすくなります。
ただし、ネット上の口コミは個人の感じ方に差があるため、複数の情報源を見比べることが大切です。
公式サイトに掲載されている症例数や実績を合わせて確認すると、より客観的に判断できると言われています。
#膝痛 #病院選び #整形外科 #リハビリ #膝関節専門医
5.病院に行く前・行った後にできる膝ケア&再発予防

膝が痛くなったとき、病院での検査や施術も大切ですが、日常生活の過ごし方が改善のカギになることも多いです。
ここでは、来院前にできるセルフケアから、受診後のリハビリ・再発予防のポイントまで、無理なく続けられる方法を紹介します。
受診前にしておきたいセルフチェック・痛み軽減法(体重管理・姿勢改善など)
「まだ病院へ行くほどでは…」と思っても、膝に違和感を覚えた時点でセルフチェックをしてみることが大切です。
例えば、
軽い痛みであれば、まずは体重管理を意識してみましょう。体重1kgの増加が膝への負担を約3kg増やすとも言われており、少しの減量でも負担を軽減できる場合があります。
また、デスクワークなどで猫背になっていると、重心が前に傾き膝に負担が集中します。姿勢を正すだけでも痛みが軽くなるケースもあるようです。
(引用元:足立慶友整形外科 https://clinic.adachikeiyu.com/)
受診後に続けたいリハビリ・運動療法(膝周囲筋力強化など)
病院での施術後は、リハビリや運動療法を継続することが再発予防につながります。
特に重要なのは、膝関節を支える「太ももの前側(大腿四頭筋)」と「お尻まわり(中殿筋)」の筋肉を鍛えること。
椅子に座って片足を伸ばす「レッグエクステンション」や、仰向けでお尻を持ち上げる「ヒップリフト」など、自宅でもできる軽い運動から始めるとよいでしょう。
また、リハビリでは筋トレだけでなく、膝の可動域を保つストレッチや姿勢改善の指導も行われることがあります。
郵政病院(日本郵政病院)では、保存療法の一環として理学療法士による運動指導を組み合わせることで、再発防止をサポートしていると紹介されています。
(引用元:日本郵政病院 https://hospital.japanpost.jp/tokyo/shinryo/seikei/oa.html)
日常生活で膝に負担をかけない工夫(座り方・歩き方・荷重分散)
普段の動作も、少し工夫するだけで膝の負担を減らすことができます。
例えば、
また、歩行時は「一歩を大きく出しすぎない」「かかとから着地してつま先で蹴る」という歩き方を意識しましょう。膝だけでなく股関節や足首にも均等に荷重を分散できます。
再発・進行を防ぐための定期チェック・生活習慣改善
膝の痛みは、一度改善しても再発するケースがあります。
そのため、定期的に膝の状態をチェックし、違和感が出たら早めに相談することが大切です。
ウォーキングや軽い筋トレなどを習慣化し、体のバランスを整えることも再発防止に役立ちます。
また、冷えや血流の悪化も膝の不調を引き起こす原因の一つとされているため、入浴やストレッチで体を温めることもおすすめです。
膝を守る生活習慣を積み重ねることが、長く健康に歩く第一歩と言われています。
#膝痛 #リハビリ #膝ケア #姿勢改善 #再発予防
この記事をシェアする
関連記事