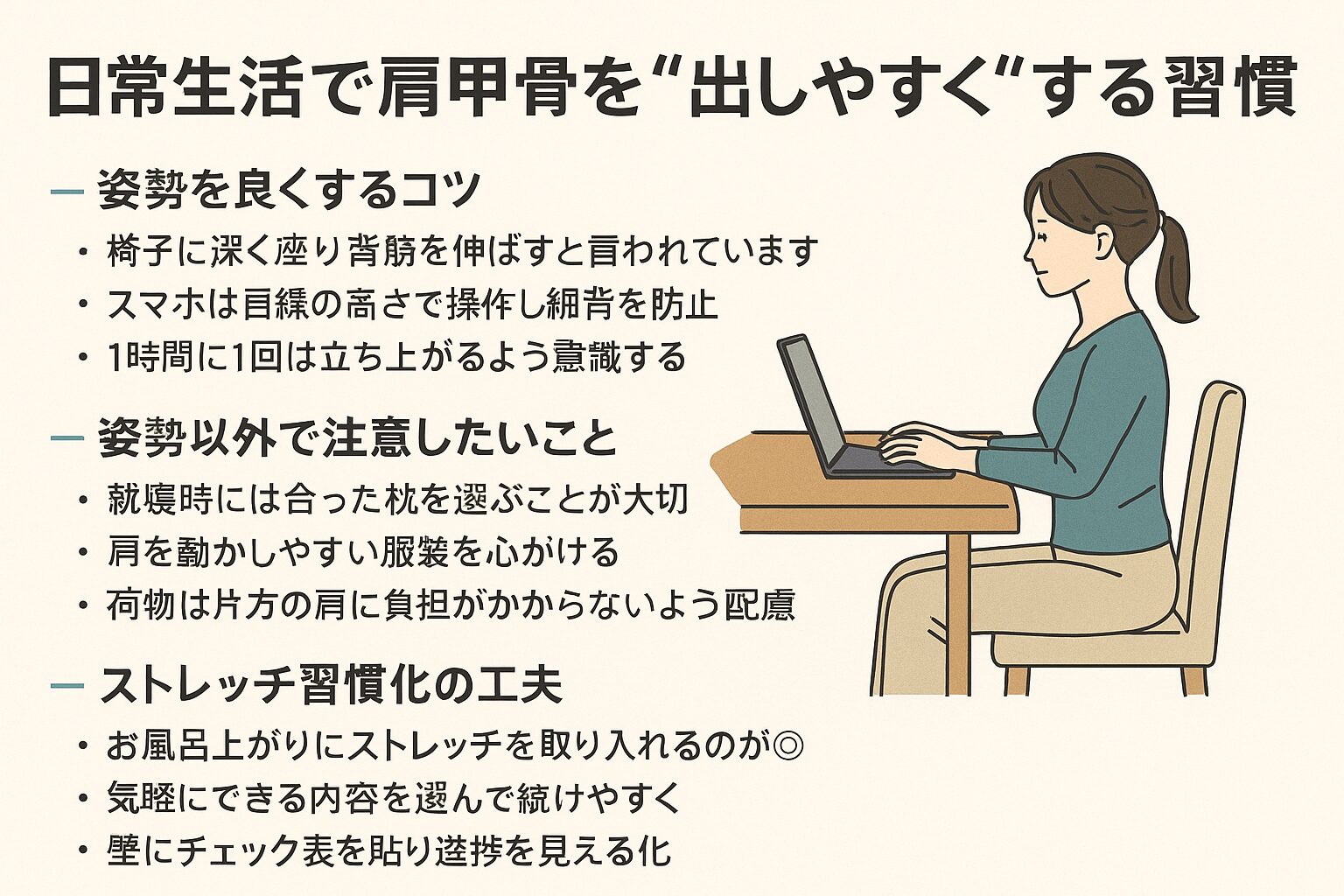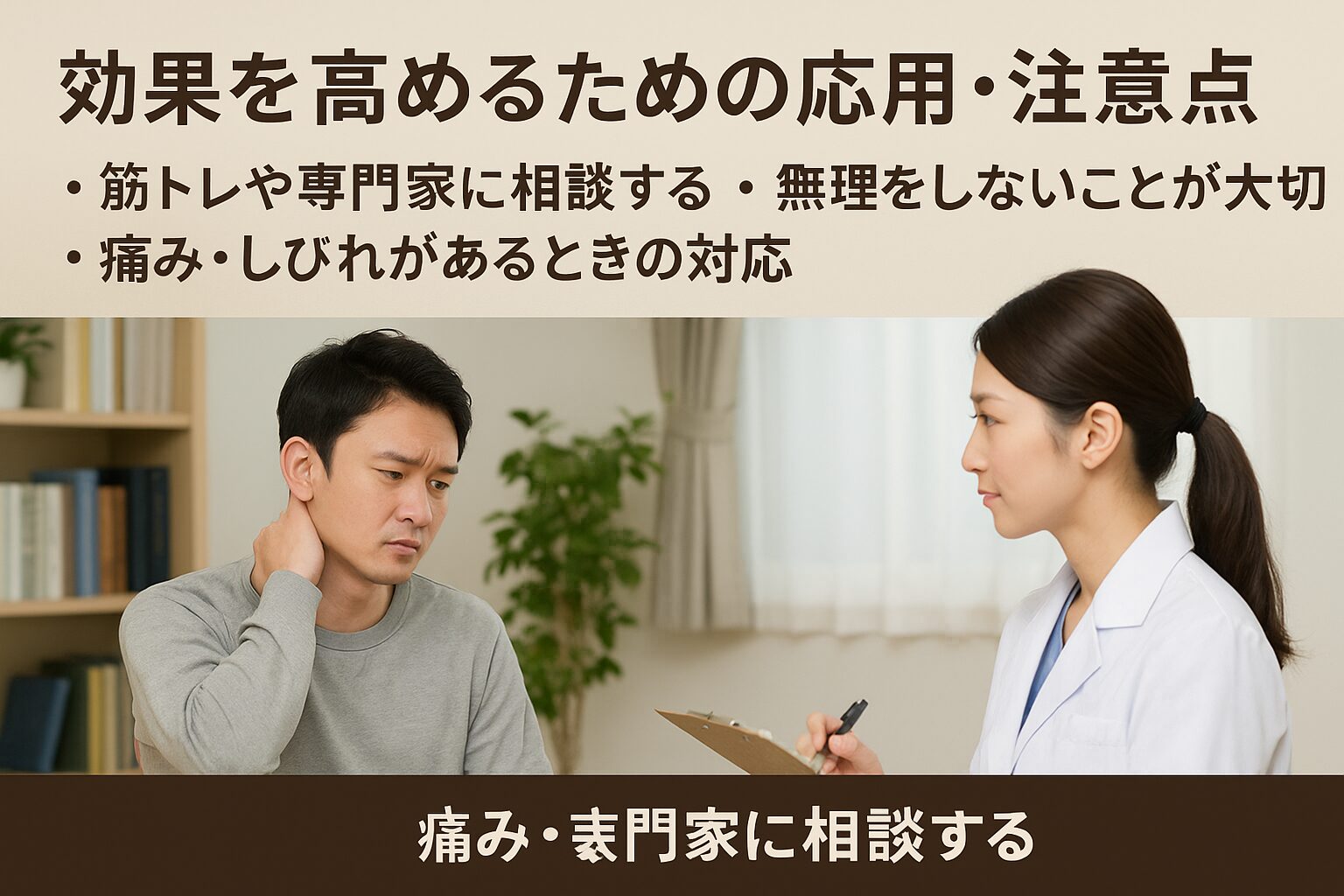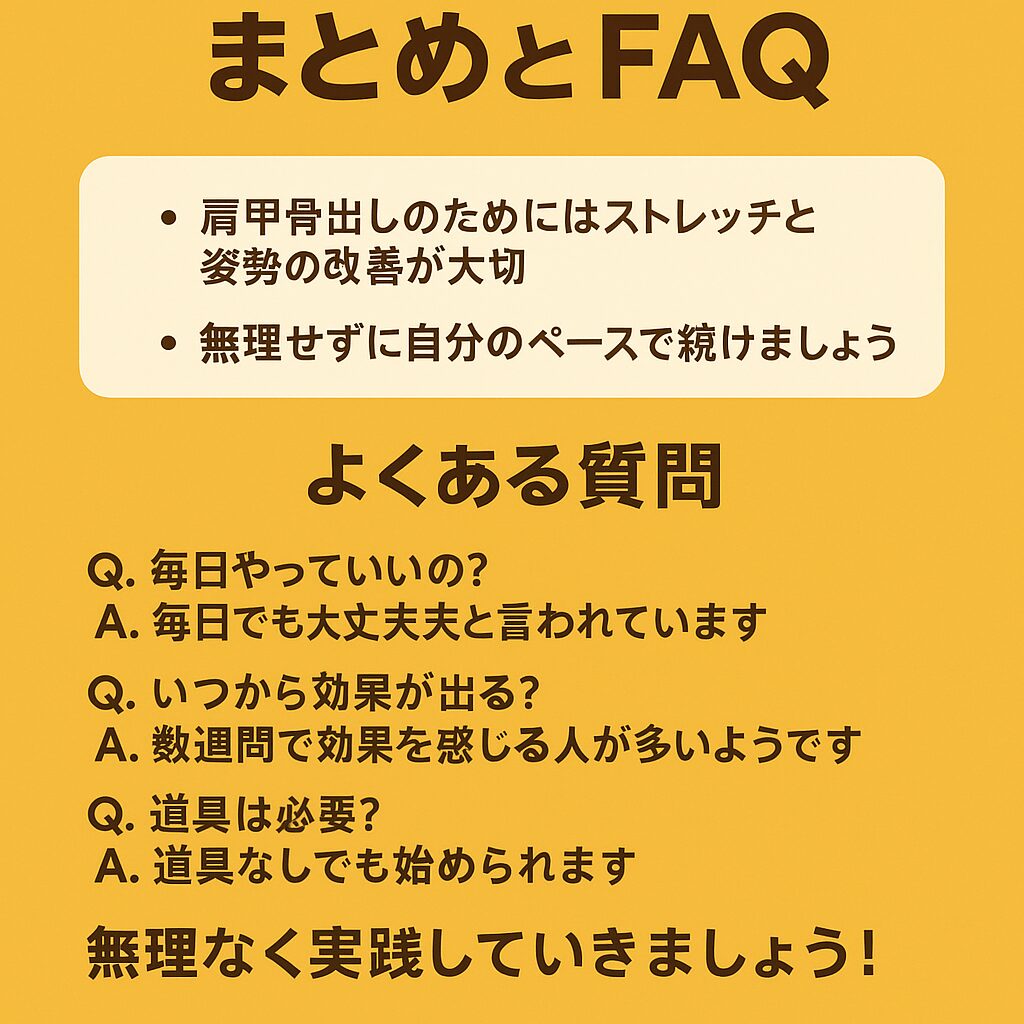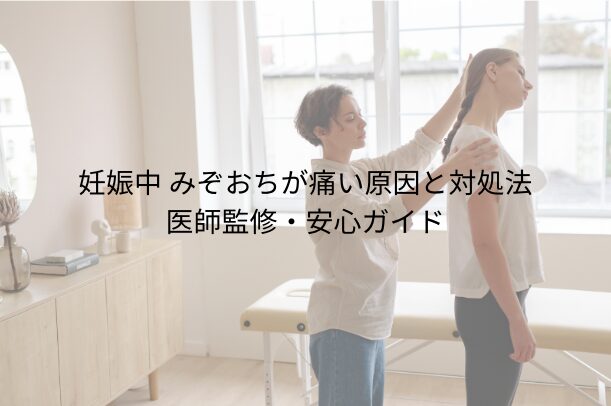柔軟性を確認するセルフチェック
「肩甲骨出し方」を実践する前に、自分の肩甲骨がどの程度動くのかを確かめることが大切だと言われています。例えば、壁に背中をつけたまま腕をゆっくりと上げ、耳の横までスムーズに伸ばせるかどうかを確認する方法があります。肩が前に出たり腰が反ってしまう場合、肩甲骨まわりの柔軟性が不足している可能性があるとされています。
また、片方の手を背中の上から、もう片方を下から回し、両手が背中で近づくかどうかを試すチェックも有効だと紹介されています(引用元:サワイ健康推進課)。
正常と改善が必要な目安
理想的には、腕を上げたときに肩甲骨がしっかりと回旋し、耳の近くまで腕が上がる状態が「正常」と言われています。一方、肩がすぐにすくんでしまったり、腕が途中までしか上がらないと、肩甲骨周囲の筋肉が硬くなっているサインとも考えられます。また、後ろで手を組むテストで手が届かない場合も柔軟性不足の目安になるとされています(引用元:アリナミン)。
左右差や日常生活でのサイン
左右の柔軟性に差があるかどうかも見逃せないポイントです。例えば、右手は背中で高い位置まで届くのに左手は届かない場合、片側の筋肉だけが固まっている可能性があると言われています。さらに、日常生活で「ブラのホックを止めにくい」「背中で手を組みにくい」「長時間のデスクワークで肩が重くなる」といった感覚がある人も、肩甲骨の動きが制限されているサインかもしれません(引用元:SIXPADコラム)。
こうしたチェックを行うことで、自分の肩甲骨の状態を理解しやすくなります。柔軟性が不足していると感じたら、無理をせず少しずつストレッチや体操を取り入れていくことが推奨されています。
#肩甲骨出し方
#柔軟性チェック
#肩こり改善
#ストレッチ習慣
#姿勢意識