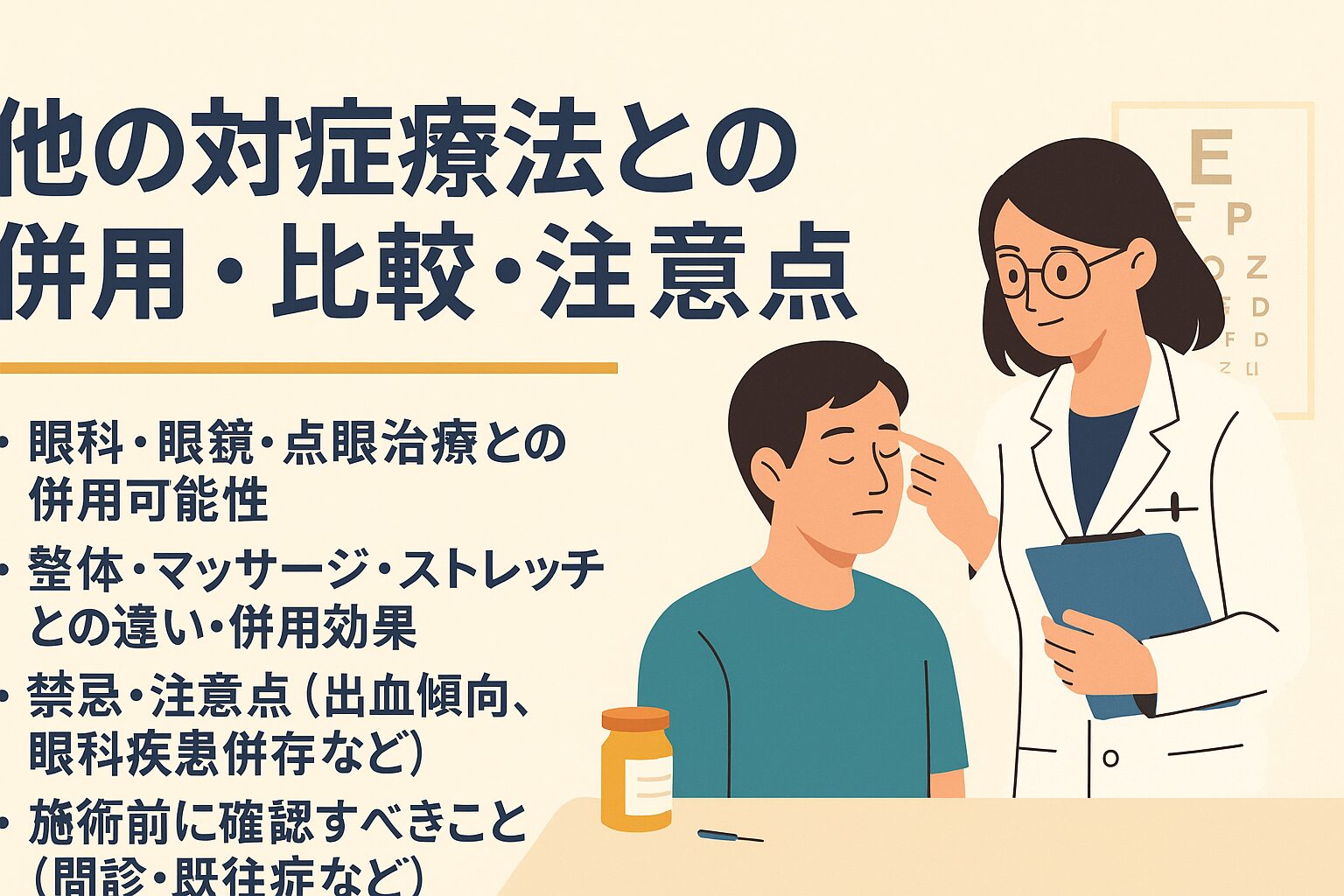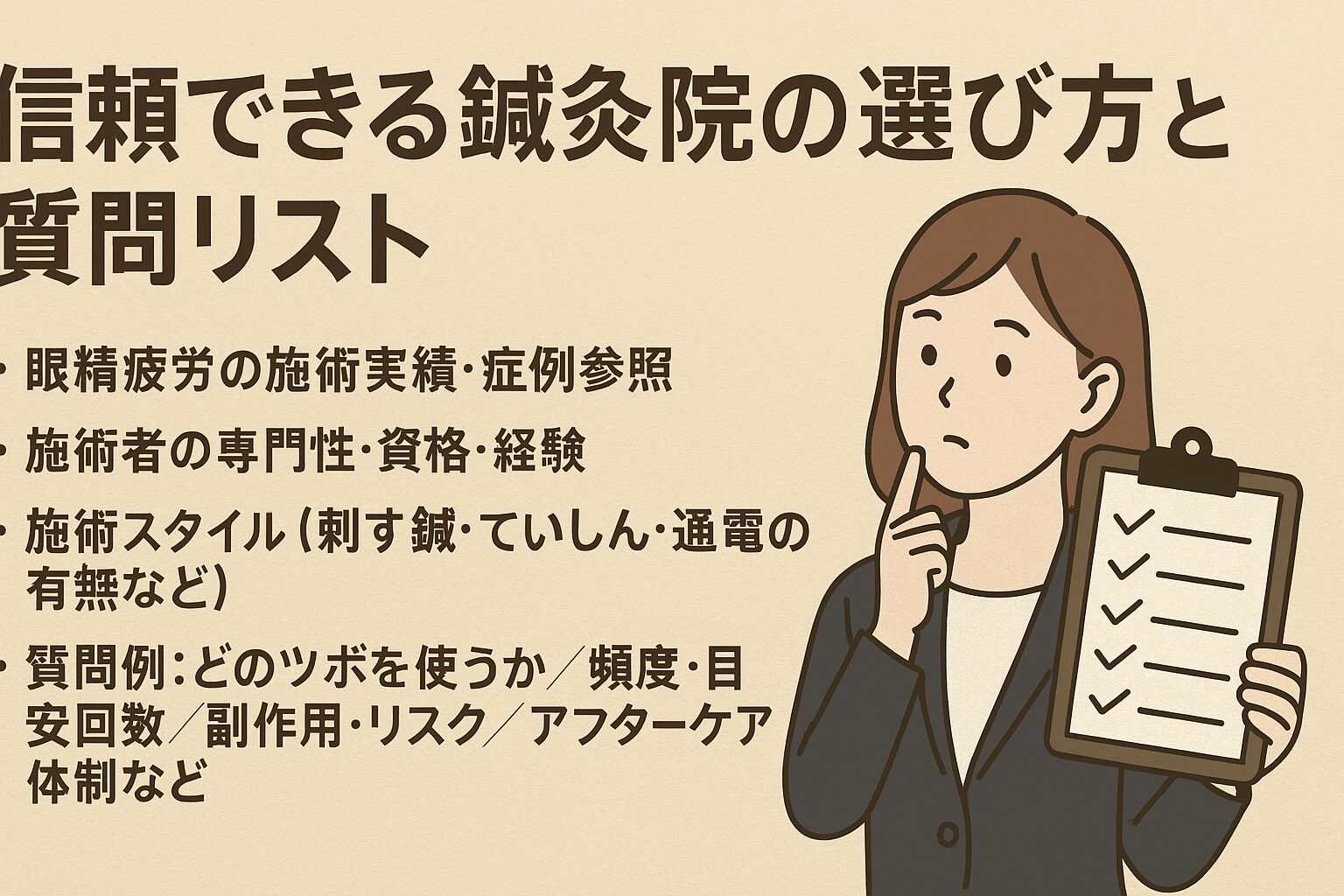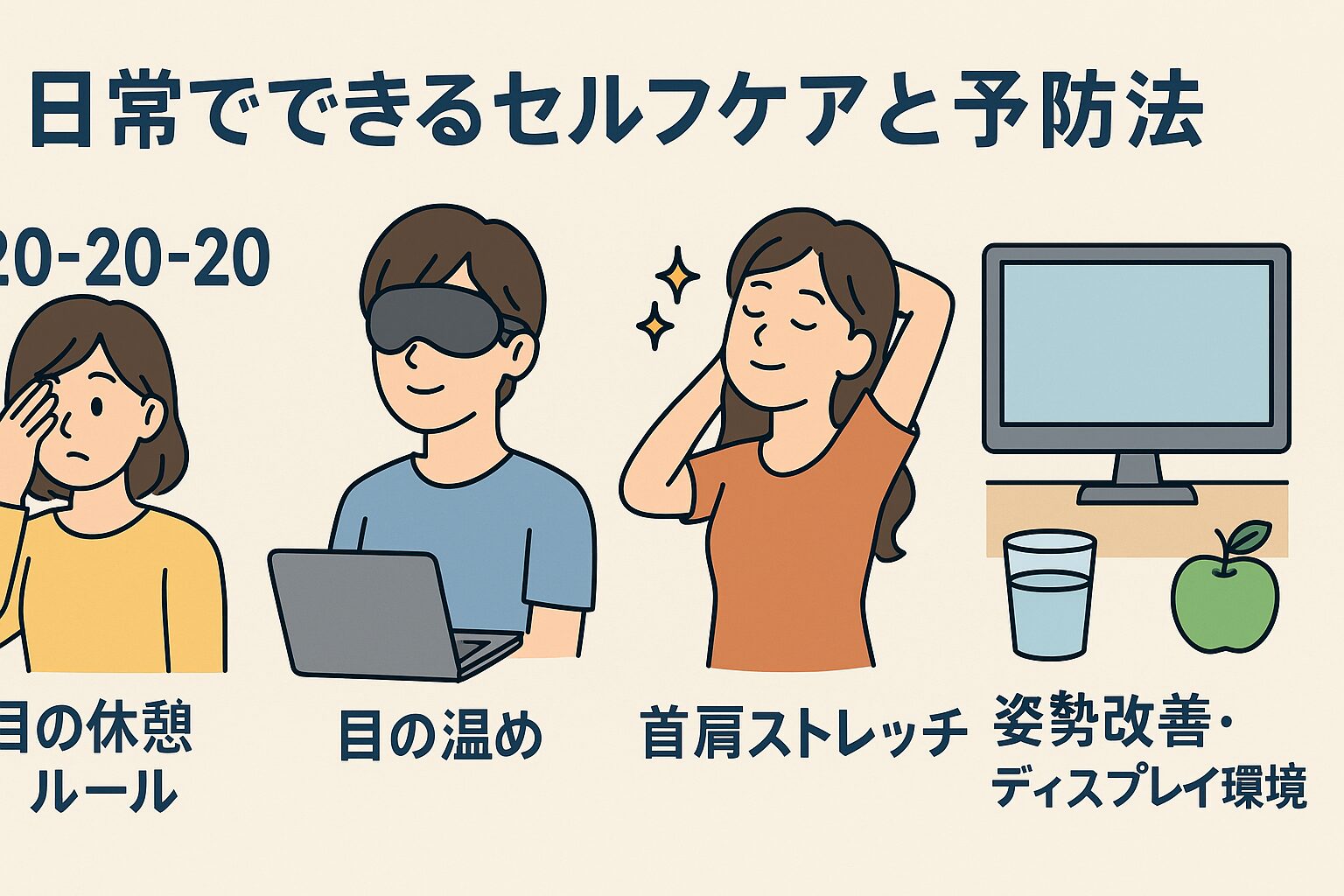1.鍼灸で眼精疲労を改善できる理由と期待できる効果
眼精疲労とは何か(定義と症状)
眼精疲労の主な原因要因(目筋疲労、血流不良、首肩コリ、自律神経の乱れなど)
鍼灸がアプローチできる領域(筋肉弛緩・血流促進・神経調整)
期待される効果(痛み軽減・かすみ改善・目の軽さ)
2.鍼灸の施術内容・ツボ/アプローチ実例
代表的なツボ・刺鍼部位(目周囲、後頭下筋群、風池、首肩など)
刺鍼/通電/お灸・ていしんなどの手法の違い
重度例の施術例(複数本刺鍼・休息を挟む手法など)
施術時間・頻度・回数の目安
3.他の対症療法との併用・比較・注意点
眼科・眼鏡・点眼治療との併用可能性
整体・マッサージ・ストレッチとの違い・併用効果
禁忌・注意点(出血傾向、眼科疾患併存など)
施術前に確認すべきこと(問診・既往症など)
4.信頼できる鍼灸院の選び方と質問リスト
眼精疲労の施術実績・症例参照
施術者の専門性・資格・経験
施術スタイル(刺す鍼・ていしん・通電の有無など)
質問例:どのツボを使うか/頻度・目安回数/副作用・リスク/アフターケア体制など
5.日常でできるセルフケアと予防法
目の休憩ルール(例:20-20-20 ルールなど)
目の温め・蒸しタオル・ホットアイマスク
首肩ストレッチ・軽い運動・頭皮ケア
姿勢改善・ディスプレイ環境見直し
生活習慣(睡眠・食事・水分)
1.鍼灸で眼精疲労を改善できる理由と期待できる効果
2.鍼灸の施術内容・ツボ/アプローチ実例

代表的なツボ・刺鍼部位(目周囲・後頭下・風池・首肩など)
では、具体的にどのあたりに鍼をするかを見ていきましょう。眼精疲労に使われやすいツボとしてよく挙げられるのは、たとえば 睛明(せいめい/目頭と鼻の間)、魚腰(ぎょよう/眉間のあたり)、瞳子髎(どうしりょう/目尻外側)、太陽(たいよう/こめかみ付近) などがあります。 グラン+1
また、目の周囲だけでなく、後頭下筋群~首の付け根あたり、風池(ふうち)、さらに首・肩・背中側も併せて刺す院も多いです。 グラン+2hari-care.jp+2
目まわりの鍼は非常に細く、浅めに刺すケースが多く、首肩~後頭部はやや深さを使うこともあります。施術院によって、目だけ・首肩込み・全身も含めるスタイルが異なります。 hari-care.jp+2グラン+2
刺鍼/通電/お灸・ていしんなどの手法の違い
鍼灸で使われる方法にはいくつかバリエーションがあります。まず「刺鍼(ししん)」は通常の鍼をツボに刺す方法です。これに 通電(電気鍼/低周波通電) を併用することがあり、鍼に微弱な電流を流して刺激を持続させたり、筋肉の収縮リズムを調整したりする技法です。通電を使うスタイルを取り入れている院もあります。 hari-care.jp+2グラン+2
また、お灸を併用する場合もあります。目の周囲や首肩に温かい刺激を加えることで血流を促す目的です。仰向けで鍼を刺した後、お灸を併用する流れを採るコースも見られます。 グラン+2hari-care.jp+2
さらに、ていしん(圧刺/ていしん法) と呼ばれる、鍼を皮膚上に軽く接触させたり、ごく浅く押すような刺激を加える手法を使う院もあります。これは刺激を弱めたい、鍼が苦手な方へ配慮した方法とされます。
要するに、刺鍼・通電・お灸・ていしんのどれを使うか、また組み合わせるかは、患者さんの状態・刺激耐性・院の方針によって変わるわけですね。
重度例の施術例(複数本刺鍼・休息を挟む手法など)
では、症状が重いケースではどうするか?オアシスはり灸治療院が紹介している例では、眼精疲労がなかなか改善しない重度例に対して、目のまわりに多数の鍼を刺したまま一定時間休む方式を採っています。たとえば、「刺したまま30分程度休んでいただく」ケースがあるとされています。 hari-care.jp
また、目・首肩など複数部位を同時に刺す“集中型”施術を行うこともあります。通常より本数を多くして広めにアプローチするわけです。こうした方法は、一般的な軽度〜中等度向け施術よりも刺激量を増やす方向になるため、鍼の太さ・深さ・休息挟み方などを慎重に設計しているようです。 hari-care.jp+2グラン+2
重度例では、一回で劇的に改善することを狙うより、反応を見ながら複数回の施術+休息時間を設けながら負荷を調整する方針を立てる院が多いようです。
施術時間・頻度・回数の目安
最後に、施術の時間・頻度・通院回数の目安です。グラン治療院では、眼精疲労特化型コースを 30分・6,800円 で提供している例があります。 グラン
オアシスはり灸では「目の標準治療コース」が、目まわり+首肩背中を含めたオーダーメード施術になっており、時間枠はその院の判断によるものとされています。 hari-care.jp+1
通う頻度としては、最初の1〜2週間に 週1回または隔週で施術を重ね、その後、改善傾向が見られれば 2〜4週間に1回程度へ移行するケースが多いようです(ただし、症状や体力・反応によって変動します)。
回数としては、軽度〜中等度であれば 5~8回ほど続けてみることを目安とする院が多く、一方で慢性化・重度例では 10回以上の継続を見越してプランを立てるところもあります。
ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、実際には鍼灸師とのカウンセリング・反応を見ながら調整していくことが重要です。
#鍼灸
#眼精疲労
#ツボ刺激
#通電鍼
#重度例
3.他の対症療法との併用・比較・注意点

眼科・眼鏡・点眼治療との併用可能性
「眼精疲労だから鍼灸だけ」ではなく、眼科的アプローチと併用するケースも多くあります。例えば、ドライアイや緑内障など眼科疾患を併存している場合は、点眼薬がメインの対処となることが通常です。そのうえで、鍼灸をサポート的に併用することで、眼底循環を促し、点眼治療の補助になる可能性が指摘されています。引用元:箱嶌医針堂「鍼灸治療の文献では、…点眼薬と併用して治療を行うことが有効であるとされています」 横浜の鍼灸〖土井治療院〗
ただし、鍼灸を受ける際には、眼科医の許可を得てから行う方が安心です。特に眼圧が高い/視野に異常が見られるようなケースでは、まず眼科で現状を確認することが望ましいです。
整体・マッサージ・ストレッチとの違い・併用効果
整体やマッサージ、ストレッチは筋肉のこりや姿勢のゆがみを緩め、血流を改善する点で、鍼灸と親和性があります。たとえば、頸部・肩甲骨周辺のコリをストレッチでほぐしてから、鍼灸でツボを刺激する併用スタイルを取る院もあります。引用元:鍼灸院 Ouchi (“鍼灸施術だけではなかなか解消できない事が有るため、ストレッチを取り入れ … より効率の良い施術効果が得られる” ) ouchi-hariq.jp
ただし違いとして、マッサージ/整体の手技は物理的圧をかける点が強く、目の近辺には刺激を強くしづらいという制約があります。一方、鍼灸はピンポイントで微細な刺激を与えやすいため、目周囲の細かい筋・神経にアプローチしやすいという特徴があるとされています。引用元:三越前はり灸整骨院「鍼を一定の深さで刺し、15〜30分間放置します」 mitsukoshi-seikotsuin.com
併用時には、整体・マッサージで大きな緊張を取り、鍼灸で微調整をするという流れにすることで、相乗効果を狙う院もあります。
禁忌・注意点(出血傾向、眼科疾患併存など)
鍼灸を行ううえで避けた方が良い条件もいくつかあります。たとえば 凝血機能異常(出血傾向のある体質)や抗凝固薬使用中の方 は、鍼による出血リスクを考慮する必要があると言われています。引用元:百度健康「凝血功能异常(如血友病)或长期服用抗凝药物」 health.baidu.com
また、眼部に 炎症・感染(結膜炎・麦粒腫など) がある場合、その部位への鍼灸刺激は避けたほうがよいとされています。引用元:同上 health.baidu.com
さらに、緑内障や網膜疾患、眼圧異常を伴う疾患 を抱えている方は、鍼灸を行う前に眼科で検査・評価を受けるべきです。引用元:箱嶌医針堂、Ouchi など 横浜の鍼灸〖土井治療院〗+1
妊娠中や重篤な高血圧、てんかん既往のある方も、施術可否を慎重に判断する必要があります。
施術前に確認すべきこと(問診・既往症など)
安全性を高めるため、施術前には以下をしっかり確認することが望ましいです。
-
既往症や服薬歴(抗凝固薬・血液疾患・眼科疾患など)
-
眼科での最近の検査データ(眼圧、視野、網膜病変など)
-
目まわりの皮膚状態(炎症・湿疹・感染兆候など)
-
アレルギー歴や金属過敏症(鍼素材に対する反応確認)
-
刺鍼による刺激の許容度(痛みが苦手かどうか)
-
事前に眼科医との相談可否
これらを問診で確認したうえで、安全ラインを超えない刺激設計にするのが、信頼できる施術者の姿勢と言われています。
4.信頼できる鍼灸院の選び方と質問リスト

眼精疲労の施術実績・症例参照を確認しよう
まず、院を選ぶ際に重視したいのが 眼精疲労に関する施術実績 です。「目・眼精疲労」などのキーワードで過去の 症例写真・体験談・改善例 を公開しているかをチェックするといいでしょう。多くの鍼灸院は、Webサイトで「〇〇件の改善例」「施術前後の写真」「利用者の声」などを載せています。たとえば「眼精疲労 特化コース」や「目の疲れ」「視界改善」などの実績記載がある院は、目の症状に関してある程度の臨床経験がある可能性が高いと言われています。引用元:成竹鍼灸整骨院「鍼灸院の選び方」などで、専門性・説明対応を重視するという記述があります。step-kisarazu.com
また、単に症例があるだけでなく、「どのような症状から始まったのか」「どれくらいの期間通って改善したのか」といった 改善過程 が提示されていると信頼性が増します。
施術者の専門性・資格・経験を確認しよう
院側が掲示する はり師・きゅう師資格証、あるいは 学会所属・研修歴・専門領域 の情報は、安心感を高める材料になります。国家資格を持っていることは当然ですが、目の疲れ・眼精疲労という専門分野に対して関心を持って研鑽しているかどうかを見たいところです。
経験年数や、これまでどのような症例を扱ってきたか、また 美容鍼 を扱っているなら顔面構造の理解も期待できるという観点が、業界で語られる選び方の条件の一つになっています。鍼灸院が「美容鍼対応」を明記していれば、顔面筋肉の理解がある可能性を示している、という見方もあります。江東区南砂と東砂と塩浜の成竹鍼灸整骨院グループ |+1
さらに、施術者が自らブログやコラムで眼精疲労について語っているか、学術発表をしているかなども目を通すといいでしょう。
施術スタイル(刺す鍼・ていしん・通電の有無など)を把握する
施術方法にも違いがあります。「刺す鍼」を主体とするところ、「ていしん(浅刺し・接触刺鍼)」を併用するところ、「通電(電気鍼)」を使うところ、また「お灸」「熱刺激併用」などのスタイルを持つ院もあります。
たとえば、刺激に弱い体質の人には、ていしん主体または通電なしの穏やかなスタイルの院が選ばれやすいです。逆に、しっかりとした刺激・調整を好む人には通電併用の施術を使う院が適するかもしれません。
このスタイルを事前に理解しておくと、「思っていた刺激感と違う」「痛すぎた/効果が弱かった」と感じるミスマッチを減らせます。
質問例:施術前に聞いておきたいリスト
来院前または初回時に、次のような質問を施術者に投げかけておくと安心です。
質問内容 なぜ聞くのか
「どのツボを使いますか?(例:風池・睛明など)」 使用ツボにより方針や狙いが透けて見える
「通電やお灸は併用しますか?」 刺激強度や施術スタイルの確認
「頻度・目安回数は?」 通院ペースや改善目安を把握するため
「副作用・リスクはありますか?」 出血・内出血・体調変化などの注意を事前把握
「アフターケア体制はありますか?」 日常ケア指導・フォローアップ体制の有無確認
これらの質問をきちんと受け答えしてくれる施術者は、 信頼度が高い可能性 があると言われています。
#眼精疲労 #鍼灸院選び #専門性 #施術スタイル #質問リスト
5.日常でできるセルフケアと予防法

目の休憩ルール(例:20-20-20 ルールなど)
パソコンやスマホ作業を長く続けていると、「あ、もう目が重い……」と感じること、ありますよね。そんなときに取り入れたいのが 20-20-20 ルール です。具体的には、作業を20分ほど続けたら、20秒間だけでも遠く(約6メートル先=20フィート)を見ることで、目の筋肉をリラックスさせるという方法です。米国眼科協会などでも推奨されていて、「近景ばかり見続けるストレスを軽減する助けになる」と言われています。引用元:LifeHacker「20-20-20ルールとは?」 ライフハッカー・ジャパン
ただ、きっちりこの数字じゃなくてもいいという声も多くて、「30分に1回」「15分ごと」など、自分のリズムにあわせて遠くを見る休憩を入れる形でも有効とされています。引用元:Serai「スマホで疲れた目に 20・20・20ルール」 サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト
目の温め・蒸しタオル・ホットアイマスク
目周りを優しく温めるだけでも血流が促されて、疲れ目感を和らげる可能性があります。蒸しタオルやホットアイマスクは、目まわりに心地よいぬくもりを届け、筋肉をリラックスさせるサポートになると言われています。例えば、目を閉じてホットアイマスクを10分ほど当てるだけでも、ほっと一息つくようなケアになります。
ただし、温めすぎないように注意が必要です。火傷や過剰刺激にならないよう、温度をチェックする、時間を守るなどの配慮が大切です。
首肩ストレッチ・軽い運動・頭皮ケア
目が疲れると、首・肩まわりのコリも同時に感じることが多いですよね。首をゆるやかに左右に倒すストレッチ、肩を回す運動、背筋を伸ばす軽い体操などを合間に取り入れるだけでも、血行を促して目まわりの負担を減らす助けになるとされています。
また、頭皮マッサージなどで頭部の血流を整えるケアも、眼精疲労の予防や軽減に役立つ可能性があります。頭部~首筋を優しくほぐすようなケアがいいでしょう。
姿勢改善・ディスプレイ環境見直し
意外と見落としがちですが、姿勢と画面環境の見直しは非常に重要です。画面を近すぎに置いたり、顔を画面に近づけすぎたりする姿勢は、目への負担を強めます。文部科学省系のガイドなどでも、「画面までの距離は30センチ以上離す」ことを推奨しており、画面の反射や光の角度にも注意を促しています。引用元:gankaikai “GIGA マニュアル PDF” gankaikai.or.jp
椅子と机の高さを調整し、画面は目線より少し下に置く、照明を適度にするなど、デスク環境を整えることで目へのストレスはだいぶ軽くなります。
生活習慣(睡眠・食事・水分)
最後に、目の状態を土台から支える生活習慣も無視できません。質の良い睡眠を確保すること、ビタミンA・C・E やオメガ3 脂肪酸を含む食材を意識的にとること、水分補給をちゃんとすることなどは、目の健康維持にプラスになると考えられています。
また、規則正しい生活リズム、ストレス管理、適度な運動習慣を持つことも、全体の体の血流・代謝を支える意味で、眼精疲労を起こしづらい体をつくる一助になると言われています。
#セルフケア #眼精疲労予防 #ホットアイマスク #ストレッチ #姿勢改善
この記事をシェアする
関連記事