- 営業時間9:00 〜12:00/ 14:00〜19:30
- 最終受付時間19:00
- 定休日木・日・祝
兵庫県姫路市別所町北宿1046−3
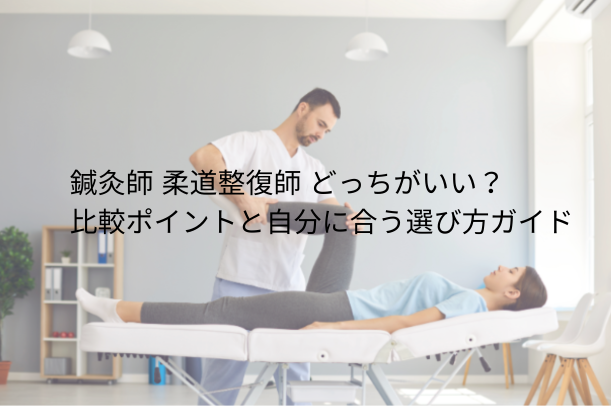
両者の定義、法的根拠、国家資格の概要。例:鍼灸師はツボ・経絡による東洋医学的治療、柔道整復師は骨・関節・筋・靭帯への整復・固定など。
急性外傷 vs 慢性不調、使う技術(鍼・灸・手技・器具等)、対応可能な症例、施術スタイルの違い
養成機関・学科・実技・筆記試験、課程年数、合格率の傾向、費用、勉強の難しさ
平均年収・初任給・地域差、正社員 vs 開業、勤務先(鍼灸院・接骨院・病院 etc)、副業・兼業の可否
自分の性格・興味・強みからどちらが合いそうかを判断する軸、ダブルライセンス(両方取得)という選択肢、リスク・メリット比較

鍼灸師は、東洋医学の理論に基づき「気・血・水(きけつすい)」のバランスを整えることを目的としています。
髪の毛ほどの細いはりを用いたはり施術や、温熱刺激を与えるお灸などで、体の不調を和らげるサポートを行うのが特徴です。肩こりや冷え、慢性的な疲労感など、「なんとなく不調」と感じる状態にアプローチするケースが多いと言われています。
国家資格としては「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)」に基づいており、専門の養成学校で3年以上学び、国家試験に合格することで資格を得られます。
近年では美容鍼や不妊サポートなどの分野にも広がりを見せ、医療だけでなく健康増進やリラクゼーションの側面でも注目を集めています。
(引用元:日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、東京医療専門学校 https://www.tokyoiryo.ac.jp/)
一方、柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲など、急性の外傷に対して施術を行う専門家です。
柔道の「整復技術」に由来しており、体の構造や運動機能を理解したうえで、包帯やテーピングなどを用いながら体の回復を促します。整骨院や接骨院での勤務が多く、外傷を中心に対応するケースが一般的です。
この資格は「柔道整復師法(昭和45年法律第19号)」に基づいており、こちらも国家資格です。3年以上の専門課程で、解剖学・生理学・運動学などの医療基礎科目を学び、国家試験に合格することで資格を取得できます。
スポーツ分野や介護・リハビリ領域でも活躍の場が広がっており、「ケガに強い施術者」として信頼を集めています。
(引用元:公益社団法人 日本柔道整復師会 https://www.japanpt.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、呉竹学園 https://www.kuretake.ac.jp/)
両者とも「国家資格でありながら、医師とは異なる独自の専門性を持つ」点が共通しています。
ただし、鍼灸師は東洋医学的なバランス改善を目的とするのに対し、柔道整復師は外傷の整復や機能回復を支援するという違いがあります。どちらが「良い・悪い」というよりも、自分がどんな領域に関心を持ち、どんな人をサポートしたいかによって選び方が変わると言われています。

鍼灸師は、長年続く肩こりや冷え、頭痛、だるさなど、いわゆる「未病」と呼ばれる慢性不調に対応すると言われています。
髪の毛ほどの細いはりを体のツボに刺すはり施術、または艾(もぐさ)を燃やして温熱刺激を与えるお灸によって、体内の「気・血・水(きけつすい)」の流れを整えることを目指します。
たとえば、デスクワークで目の疲れが強い人や、冷えや生理痛がつらい人など、体質や自律神経の乱れが関係しているケースに用いられることが多いようです。
使用する道具は、はり・お灸・温灸器・低周波鍼通電装置などで、施術後には体が温かく感じる人も多いと言われています。
鍼灸は「体のバランスを整えて自然回復力を高める」というアプローチが特徴で、医療行為とは異なる「東洋医学的ケア」の位置づけです。
(引用元:日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、メディカルジャパン立川 https://medical-japan.net/)
柔道整復師は、転倒やスポーツ中のケガなど、**急に発生した外傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲など)**を対象としています。
整骨院や接骨院で見かける「テーピング」「包帯固定」「手技による整復」などは、まさに柔道整復師の技術です。
特にスポーツ現場では、試合中にケガをした選手への応急対応や、回復をサポートする施術などを行うケースも多いと言われています。
施術では、骨格や筋肉のバランスを見極めながら、体の動きを正しく戻すことを重視します。使用する技術は手技・固定・電気刺激機器など。
また、柔道整復師は医師の同意があれば健康保険を使って施術を行うことも可能で、より医療寄りのサポートを行う立場にあります。
(引用元:日本柔道整復師会 https://www.japanpt.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、呉竹学園https://www.kuretake.ac.jp/)
鍼灸師は「慢性不調の改善をめざす穏やかな施術」が中心で、柔道整復師は「ケガなどの急性症状への対応」に強いと言われています。
前者はリラクゼーション的な雰囲気の鍼灸院が多く、後者は運動やリハビリの現場でも活躍しています。
どちらを選ぶかは、「今の自分の体の状態」によって変わるものです。慢性的な疲労や冷えに悩む人は鍼灸師、ケガや関節の痛みに困っている人は柔道整復師に相談するのが良いとされています。
それぞれが得意とする領域を理解しておくことで、より自分に合った施術を受けやすくなるでしょう。

鍼灸師を目指すには、「はり師」「きゅう師」それぞれの国家資格を取得する必要があります。
文部科学省・厚生労働省が認可した専門学校や大学の鍼灸学科に3年以上通学し、解剖学・生理学・経絡学などを学びます。授業では実技が多く、実際に鍼を扱う練習やツボの位置を覚える訓練も行われます。
国家試験は筆記と実技を含み、毎年2月頃に実施されます。合格率はおおむね70〜85%前後で推移しており、しっかりと勉強を重ねれば合格を狙えると言われています(引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp/、呉竹学園 https://www.kuretake.ac.jp/)。
学費の目安は総額で400〜600万円前後が一般的です。大学進学コースではさらに高くなることもありますが、専門学校では夜間部を選ぶことで費用を抑える方法もあります。
また、東洋医学の奥深さに惹かれる人が多く、心理学や体質学なども幅広く学ぶのが特徴です。
柔道整復師の養成課程も3年以上で、こちらは筋肉や骨、関節の構造といった運動器系の解剖学・生理学を中心に学びます。
実技ではテーピング、包帯、整復法、固定法などの技術を反復練習し、骨折や脱臼などの外傷対応に必要なスキルを身につけます。
国家試験は毎年3月頃に実施され、合格率は60〜80%程度とやや幅があります。年によって難易度が変わる傾向があるとも言われています(引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、日本柔道整復師会https://www.japanpt.or.jp/、東京メディカル・スポーツ専門学校 https://www.tokyo-medical.ac.jp/)。
学費は450〜650万円程度が目安で、学科によっては実技設備や教材費が別途必要な場合もあります。
実際の臨床現場を想定した実習も多く、即戦力として働けるように指導が行われるのが特徴です。
「どちらが難しいか?」という質問には一概に答えづらいですが、傾向としては以下のように言われています。
鍼灸師: 東洋医学理論を理解し、ツボの位置や経絡を覚える根気が必要。細かい作業が得意な人に向いている。
柔道整復師: 骨格や筋肉の構造を理解し、力学的思考が求められる。実技を通じて体で覚えるのが得意な人に合いやすい。
いずれも人の体に直接関わる資格なので、**「体を良くしたい」「手技を通して支えたい」**という思いを持つことが、学びを続けるモチベーションにつながると言われています。

鍼灸師の平均年収はおよそ350〜450万円前後とされています(引用元:日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、東京医療専門学校https://www.tokyoiryo.ac.jp/)。
ただし、これは勤務形態や地域によって大きく差があります。都市部の鍼灸院や美容鍼灸を取り入れている店舗では、月収40〜50万円を超えるケースもあると言われています。
勤務先としては、鍼灸院・整骨院・美容サロン・病院のリハビリ部門・介護施設などが中心。中にはスポーツチームの専属スタッフや訪問鍼灸として在宅ケアに関わる人もいます。
また、鍼灸師は独立開業しやすい資格の一つです。
自宅サロンやレンタルスペースで開業する人も増えており、開業後は自費施術中心のため、集客力やマーケティング次第で年収600〜800万円を目指せるとも言われています。
一方で、患者数が安定するまでは収入の波がある点には注意が必要です。
柔道整復師の平均年収は350〜500万円程度で、初任給は20〜25万円前後が多いようです(引用元:日本柔道整復師会 https://www.japanpt.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、リジョブ https://relax-job.com/)。
こちらも勤務先の種類によって収入が変わります。
もっとも一般的なのは整骨院・接骨院勤務で、柔道整復師法に基づく施術(骨折・脱臼・打撲・捻挫など)を行います。保険適用の施術を扱うことができるため、安定した来院数を見込める反面、保険請求業務や制度の理解が求められます。
さらに、病院のリハビリ科・スポーツチーム・介護施設などでも需要があり、特にスポーツ現場ではケガ予防やコンディショニング指導など、活躍の場が広がっています。
柔道整復師も将来的に独立開業が可能ですが、開業する際は実務経験や保険取り扱いの申請など、一定の条件を満たす必要があります。
どちらの職業も、副業や兼業がしやすい点が魅力です。
たとえば鍼灸師は、休日に出張施術を行ったり、美容サロンと提携してフリーランス活動をするケースがあります。
柔道整復師の場合は、スポーツトレーナー業務やパーソナルトレーナー資格と組み合わせることで、副収入を得る人も少なくありません。
「安定重視なら整骨院勤務」「自由度や専門性を重視するなら鍼灸院での独立」など、自分の価値観に合わせた働き方を選べるのが魅力です。
どちらも“人の体に寄り添う仕事”として、技術と信頼を積み重ねることでキャリアアップが可能だと言われています。

鍼灸師は、東洋医学の考え方を基盤に「体全体のバランス」を整える施術を行います。
そのため、観察力や聞き取り力があり、人の小さな変化に気づける人が向いていると言われています。
たとえば、「相手の話をじっくり聞いて原因を探るのが得意」「手先が器用で細かい作業が好き」という人にはぴったりです。
また、鍼やお灸などの施術は集中力を必要とするため、コツコツ型の性格の人にも合いやすい傾向があります。
近年では美容・妊活・ストレスケアなど多分野での需要も高まり、女性鍼灸師の活躍も増えています。
施術を通して「体質や生活習慣の改善をサポートしたい」という想いがある人に向いていると言われています。
(引用元:日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp/、東洋医療専門学校 https://www.toyoiryo.ac.jp/、メディカルジャパン立川 https://medical-japan.net/)
柔道整復師は、捻挫や打撲などの急性外傷に対して施術を行う“運動器の専門家”です。
体を動かすことが好きで、スポーツやリハビリ分野に興味がある人には特に人気があります。
例えば、「人を励ますのが得意」「チームプレーが好き」「現場で体を動かしながらサポートしたい」というタイプに合うと言われています。
実際、スポーツトレーナーとしてプロチームに関わる柔道整復師も多く、現場志向の強い職業です。
また、骨や筋肉など解剖学的な知識を重視するため、理論的に物事を考えるのが得意な人にも向いています。
将来的に整骨院や介護分野、スポーツ施設など幅広い現場で働ける自由度も魅力の一つです。
(引用元:日本柔道整復師会 https://www.japanpt.or.jp/、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/、呉竹学園https://www.kuretake.ac.jp/)
最近では、「鍼灸師+柔道整復師」のダブルライセンスを取得する人も増えています。
両方を持つことで、急性外傷から慢性不調まで幅広く対応でき、施術の自由度や収入の安定性が高まると言われています。
ただし、どちらも3年以上の専門課程が必要なため、取得には時間と費用がかかります。
それでも「一生モノの資格」として、キャリアの選択肢を広げたい人にとっては大きなメリットがあります。
一方で、開業を目指す場合は経営スキルやマーケティング知識も必要になるため、学び続ける姿勢が大切です。
(引用元:東洋医療専門学校 https://www.toyoiryo.ac.jp/times/doublelicence/、国試黒本 https://kurohon.jp/、かる・ける https://karu-keru.com/)
最終的には、「どんな人を支えたいか」「どんな働き方をしたいか」で選ぶのがポイントです。
慢性的な不調や美容・体質改善に興味があるなら鍼灸師、スポーツ・外傷・リハビリに関わりたいなら柔道整復師を目指すのがおすすめと言われています。
もし迷う場合は、専門学校の体験授業や見学会に参加して、実際の雰囲気を感じてみるとイメージがつかみやすいでしょう。